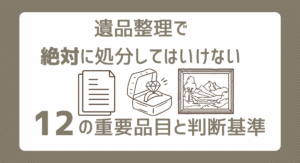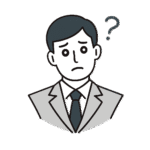
遺品整理をいつから始めるべきか悩んでいませんか?
故人を失った深い悲しみの中で、賃貸物件の退去期限や相続放棄の3ヶ月期限に追われ、親族間での話し合いもままならない状況は本当に辛いものです。
しかし、適切なタイミングを見極めることで、法的トラブルや経済的損失を避けながら、心の負担を最小限に抑えた遺品整理が可能になります。
この記事では、葬儀後の慌ただしい時期でも安心して進められる、住居状況別の開始時期判断から段階的な手順まで、初心者の方にもわかりやすく解説します。
遺品整理はいつから始める?


この章では、遺品整理を始める適切なタイミングについて紹介します。
遺品整理の開始時期には主に以下の要因が影響します。
- 住居形態(賃貸・持ち家・施設)による緊急性
- 法的期限(相続放棄3ヶ月、相続税申告10ヶ月)
- 親族の集まりやすさと合意形成のタイミング
- 遺族の心理的準備と気持ちの整理
葬儀後すぐに始めるべきケース
故人が賃貸物件に住んでいた場合や施設に入居していた場合は、葬儀が終わった直後から遺品整理を開始する必要があります。
賃貸物件では故人の死亡後も賃貸契約が継続し、家賃が毎月発生し続けるため、経済的負担を避けるために早急な対応が求められます。
また、介護施設や病院では「死亡後1週間以内に退去」といった明確な期限が設けられていることが多く、遅れると追加料金が請求される可能性があります。
故人が賃貸アパートに住んでいた場合、月末までに遺品整理を完了させるか、翌月分の家賃を支払って翌月末までに整理するケースが一般的です。
遠方に住む親族が多い場合は、葬儀で親族が集まる機会を活用して、形見分けや遺品整理の方針について話し合いを行い、役割分担を明確にすることが重要です。
四十九日法要後に始めるケース
四十九日法要後に遺品整理を始めることが最も一般的で推奨される方法です。
仏教では故人の魂が四十九日まで現世にいるとされており、魂が次の世に旅立つ四十九日を目安に、遺族も気持ちの整理をつけることが多いためです。
また、四十九日の法要は親族が一同に集まる貴重な機会でもあり、相続人全員で遺品整理について話し合える良いタイミングとなります。
相続人が遠方に住んでいてなかなか集まれない場合や、葬儀直後の慌ただしい時期を避けたい場合は、この時期を有効活用することができます。



四十九日法要は親族の合意形成と遺族の気持ちの整理を両立できる理想的なタイミングです。
法要前に話し合いの議題を整理し、当日は遺品整理の方針、役割分担、スケジュールについて具体的に決めることをお勧めします。
相続放棄期限前の注意点
相続放棄を検討している場合は、遺品整理を行うと民法第921条の「法定単純承認」とみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があるため、死亡から3ヶ月以内は特に慎重な対応が必要です。
相続財産を処分すると遺産を相続したとみなされるため、特に宝石や貴金属、家電製品など金銭的価値があるものの処分は絶対に避けなければなりません。
一度相続放棄の権利を失うと取り消しや撤回はできないため、不用意な行動は避けるべきです。
ただし、生鮮食品など日持ちしないものや、写真・手紙など明らかに金銭的価値のないものは形見分けとして処分することが可能です。
価値の判断に迷う場合は、必ず弁護士や司法書士などの専門家に相談する必要があります。
相続放棄を検討している場合は、遺品に手を付ける前に必ず専門家に相談し、どの範囲まで整理可能かを明確にしてから作業を開始することが重要です。
相続税申告期限からの逆算
相続税の申告義務がある場合は、被相続人の死亡から10ヶ月以内に申告・納税を完了させる必要があるため、遺品整理は死亡から7~8ヶ月以内に完了させることが推奨されます。
相続税申告のためには相続財産の全容把握が不可欠で、遺品整理を通じて重要書類や財産関連の遺品を発見・整理する必要があります。
通帳、印鑑、有価証券、保険証券、不動産の権利証、契約書類などの重要書類の発見・整理が相続税申告に直結するため、これらの書類を見落とすと正しい税額が算出できず、申告期限に間に合わない可能性があります。



申告書作成には相当な時間を要するため、遺産分割協議は相続開始から6ヶ月以内に完了させるのが理想的です。
相続税申告が必要な場合は、遺品整理と並行して税理士への相談を早期に開始し、重要書類の発見・整理を優先的に進める計画的なアプローチが必要です。
気持ちの整理がついてから始める判断
遺品整理に法的な期限はないため、遺族の気持ちが落ち着いてから始めることも選択肢の一つです。
故人を失った深い悲しみの中で無理に作業を進めると、必要なものを間違って処分してしまったり、後悔につながったりする可能性があります。



遺品整理は単なる片付け作業ではなく、故人への供養の意味も含むため、適切な心理状態で行うことが重要です。
持ち家の場合で緊急性がない状況では、遺族の心理的準備が整ってから開始することで、故人の思い出と向き合いながら丁寧に整理を進めることができます。
ただし、空き家の管理義務、固定資産税の継続、防犯上のリスクなども考慮が必要です。
気持ちの整理を優先する場合でも、最低限必要な手続きとして重要書類の確保や各種契約の解約手続きは早めに行い、本格的な整理は心の準備ができてから段階的に進めることをお勧めします。
\ 24時間365日受付中 /
住居状況別の開始時期判断


この章では、故人の住居状況による遺品整理の開始時期判断について紹介します。
住居状況別の開始時期判断には主に以下の内容があります。
- 賃貸物件での契約期限による緊急性の評価
- 持ち家での計画的な時間配分と優先順位
- 施設入居時の明け渡し規則と期限遵守
賃貸物件は契約期限を最優先
故人が賃貸物件に住んでいた場合は、退去期限や家賃負担を考慮し、1~3ヶ月以内に遺品整理を完了させる必要があり、この期限を最優先で考えなければなりません。
故人の死亡後も賃貸契約は自動的に消滅せず、相続人や連帯保証人が家賃債務を引き継ぐため、遅れるほど経済的負担が増加します。
大家や管理会社から退去期限を設定されることが多く、原状回復義務も発生するため迅速な対応が求められます。
故人が賃貸マンションを借りていた場合、葬儀を終えてから月末までに遺品整理を完了させるか、翌月分の家賃を支払って翌月末までに整理するケースが一般的です。
まず管理会社や大家に連絡して退去期限を確認し、具体的なスケジュールを立てることが重要で、期限が迫っている場合や遺品の量が多い場合は専門の遺品整理業者の活用を検討することをお勧めします。
持ち家の場合は余裕を持って計画
持ち家の場合は賃貸物件のような明確な退去期限がないため、遺族の気持ちの整理や親族間の調整を重視しながら、余裕を持った計画的な遺品整理が可能です。
持ち家や分譲マンションのケースでは、家族で今後について話し合った上で最適な方法を検討してから進めることができ、遺品整理には法律上の期限がないため、タイミングは相続人の任意となっています。
故人を偲ぶ時間を大切にしたい場合は、悲しみが癒えない中で無理に作業を進めるのではなく、一つ一つの品物と向き合う時間を持ちながら心の整理も同時に行うことができます。
品物の選別を慎重に行い、何を残し何を処分するかを親族間でじっくり話し合うことが可能です。
ただし、相続税申告期限や固定資産税の継続、防犯上のリスクなども考慮し、重要書類の確保や各種契約の解約は早めに行うことが大切です。
施設入居時の荷物引き取り期限
故人が介護施設や病院に入所していた場合、施設によって「死亡後1週間以内に退去」などの明確な期限が定められていることが多いため、最も緊急性の高いケースとなります。
施設では次の入居者への配慮や施設運営上の理由から、厳格な退去ルールが設けられており、期限を過ぎると延滞料金が発生する可能性があります。
病院では患者のベッド回転率の関係から、迅速な対応が求められるため注意が必要です。
施設入居の場合、故人の私物は比較的少量であることが多いものの、薬品や医療器具、衣類、写真などの貴重品の仕分けが必要で、施設によっては家具や電化製品の持ち込みがある場合もあり、これらの搬出作業も期限内に完了させる必要があります。
葬儀前後の慌ただしい時期に作業が必要となるため、事前に施設側と退去ルールを確認し、親族間で役割分担を明確にしておくことが重要です。
\ 24時間365日受付中 /
遺品整理を誰が行うか


この章では、遺品整理を誰が行うべきかについて紹介します。
遺品整理を誰が行うかには主に以下の内容があります。
- 法定相続人による遺品整理の法的責任と義務
- 親族間での効率的な役割分担と合意形成
- 相続放棄者の参加制限と注意すべき点
法定相続人が中心となる原則
遺品は法的には相続財産であるため、遺品整理は法定相続人が行うのが一般的です。



法定相続人とは民法で定められた相続人のことで、配偶者と血族が該当し、血族による相続順位は第1順位が故人の子供、第2順位が父母・祖父母、第3順位が兄弟姉妹となります。
故人が遺した遺品は相続人の相続財産になるため、遺品整理も相続人が行うのが適切とされています。
法律上、故人が遺したものは家財道具から小物に至るまで相続人が受け継ぐため、相続人以外の他人は勝手に処分する権利がありません。
相続財産の分割が終わってから遺品整理を行う場合には、故人の家屋を引き継いだ相続人が遺品整理をし、家を引き継がずに売却する場合には相続人全員に遺品整理の責任があります。



法定相続人が明確でない場合や、相続人全員が相続放棄をした場合は、家庭裁判所で選任された相続財産管理人が遺品整理を行うことになります。
親族間での役割分担の話し合い
遺品整理では親族全員での話し合いと納得のいく役割分担が重要で、勝手に遺品整理を始めることは絶対に避け、相続トラブルを未然に防ぐための合意形成が必要です。



他の親族や相続人にとって重要な物かもしれない物を自己判断で処分・売却してしまうと、トラブルの原因となります。
遺品整理は単なる物の処分ではなく、故人の思い出や遺志を尊重する重要な作業であるため、全員の理解と協力が不可欠です。
四十九日法要などで親族が集まる機会を活用して、誰が主導して整理を進めるか、作業分担をどう決めるか、遠方に住む親族はどう参加するかなどを具体的に話し合います。
また、形見分けの方針や貴重品の取り扱いについても事前に合意を得ておくことが大切です。



親族間の話し合いでは、遺品整理の開始時期、作業スケジュール、費用負担、業者依頼の可否などを明確に決め、可能であれば書面で記録を残しておくことで後々のトラブルを避けることができます。
相続放棄者は作業に参加しない
相続放棄をした人は、原則として遺品整理の作業に参加してはいけません。
遺品の処分を行うと法定単純承認とみなされ、相続放棄が無効になる可能性があるためです。
民法第921条によると、相続財産を処分すると遺産を相続したとみなされるため、相続放棄を予定している人が遺品整理に関わることは法的リスクを伴います。



特に金銭的価値があるものの処分は、相続放棄の権利を失う重大な行為となるため十分な注意が必要です。
相続放棄後でも、生鮮食品など日持ちしないものや、写真・手紙など明らかに金銭的価値のないものは形見分けとして引き継ぎ可能ですが、価値の判断に迷う場合は弁護士などの専門家に相談する必要があります。
相続放棄を検討している親族がいる場合は、その人は遺品整理の決定には参加できても実際の作業には参加せず、他の相続人が中心となって進める必要があります。
\ 24時間365日受付中 /
重要書類の保管方法


この章では、遺品整理で発見した重要書類の適切な保管方法について紹介します。
重要書類の保管方法には主に以下の内容があります。
- 相続手続きに必要な書類の種類と重要度による分類
- 紛失や損傷を防ぐ安全で確実な保管場所の選定
- デジタル化による長期保存と情報共有の対策
相続手続きに必要な書類の分類
遺品整理で発見された書類は、相続手続き、税務申告、資産評価の3つのカテゴリーに分類し、優先順位をつけて整理・保管することが重要です。
相続税申告に必要な書類
- 戸籍謄本
- 遺産分割協議書
- 各種評価明細書など



多岐にわたる書類が必要で、これらの書類がないと正しい税額が算出できず、申告期限に間に合わない可能性があります。
通帳、印鑑、有価証券、保険証券、不動産の権利証、契約書類などの重要書類は相続財産の把握に直結するため、最優先で確保する必要があります。
最優先書類の分類
- 遺言書
- エンディングノート
- 通帳
- 証券類
- 印鑑
- 保険証券
次に重要な書類の分類
- 不動産関連書類
- 契約書類
- 税務関連書類



その他の書類として写真や手紙などの思い出の品を分けて管理することで、効率的な相続手続きが可能になります。
紛失を防ぐ安全な保管場所
重要書類は火災や水害、盗難のリスクを避けるため、銀行の貸金庫や耐火金庫、複数の場所に分散して保管することが最も安全で確実な方法です。
相続手続きに必要な書類の中には、再発行が困難または不可能なものが多く含まれており、紛失すると相続手続き全体が滞る可能性があります。
自宅での保管は火災・水害・盗難などの自然災害や事故により一度に全てを失うリスクがあるため注意が必要です。
原本は銀行の貸金庫に保管し、コピーを自宅の耐火金庫と信頼できる親族の家に分散保管することで、万が一の事態に備えることができます。



保管場所は相続人全員に周知し、保管場所リストを作成して定期的に更新することが重要で、保管場所への立ち会い人を複数設定し、緊急時でも書類にアクセスできる体制を整えておくことをお勧めします。
デジタル化による長期保存対策
重要書類のデジタル化は、長期保存と親族間での情報共有、手続き時の効率化を実現する現代的で実用的な保存方法として推奨されます。
紙の書類は経年劣化により文字が薄くなったり、破損したりするリスクがあり、また複数の相続人が同時に必要とする場合にアクセスが困難になります。
デジタル化により、書類の劣化を防ぎ、必要な時にすぐに複数人がアクセスできる環境を整えることができます。



スキャナーやスマートフォンのアプリを使用して高解像度でスキャンし、PDF形式で保存します。
ファイル名には「通帳_○○銀行_2025年」のような分かりやすい名前を付け、クラウドストレージに保存して親族間で共有し、重要度に応じてフォルダ分けを行います。
デジタル化作業は相続手続きの早い段階で実施し、原本とデジタルデータの両方を保管することで、手続きの効率化と安全性の確保を同時に実現できます。
\ 24時間365日受付中 /
自分で行うメリット
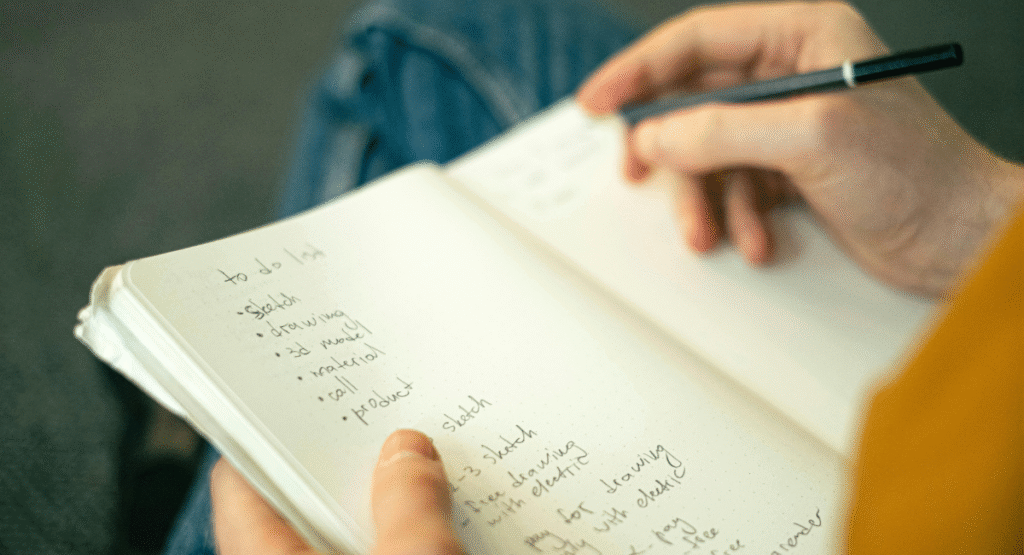
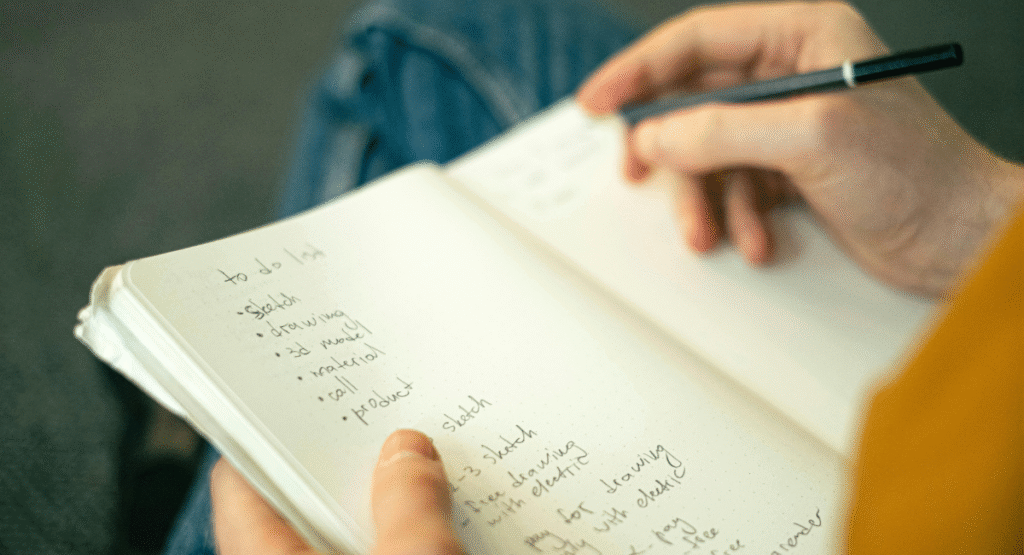
この章では、遺品整理を自分で行うメリットについて紹介します。
自分で行うメリットには主に以下の内容があります。
- 業者依頼と比較した費用面での大幅な節約効果
- 故人の思い出を大切にしながらの丁寧な整理
- 遺族の感情に配慮した自分のペースでの作業進行
メリット(1)費用を大幅に節約できる
遺品整理を自分で行うことで、業者依頼費用や不用品処分費、清掃費用などの多額のコストを大幅に節約でき、経済的負担を最小限に抑えることができます。
遺品整理業者への依頼には間取りや作業内容によって数十万円の費用が発生することが多く、特に故人の財産が少ない場合や相続財産がない場合、これらの費用負担は遺族にとって大きな経済的圧迫となります。
業者に依頼した場合の費用相場
- 1DKで15万円から
- 2DKで25万円から
- 3DKで40万円から
自分で行う場合は数万円程度の費用
- 段ボール
- ゴミ袋
- 清掃用品
- 軽トラックのレンタル費用



リサイクル可能な家電や貴金属の買取により、費用をさらに軽減できる可能性もあります。
費用節約を重視する場合は、親族で協力して作業分担を行い、重いものや専門技術が必要な部分のみ業者に部分依頼することで、コストと効率のバランスを取ることができます。
メリット(2)思い出を大切にできる
自分で遺品整理を行うことで、故人との思い出に向き合いながら一つ一つの品物を丁寧に扱い、故人への感謝と供養の気持ちを込めた整理ができます。



遺品整理は単なる物の処分ではなく、故人の思い出や遺志を尊重し、その人生をしっかりと締めくくる儀式的な役割も担っています。
業者に依頼した場合、作業効率を重視するため、思い出の品も機械的に処理されてしまう可能性があります。
写真や手紙、趣味の品、衣類などを手に取りながら、故人の生前の姿を振り返り、家族で思い出話をしながら進めることができます。
大切にしていた品物は形見分けとして適切に保存し、処分する際も感謝の気持ちを込めてお焚き上げなどの供養を行うことが可能です。
思い出を大切にしたい場合は、時間に余裕を持たせたスケジュールを組み、親族全員で故人を偲びながら作業を進めることで、心の整理と物の整理を同時に行うことができます。
メリット(3)自分のペースで進められる
自分で遺品整理を行う場合、遺族の気持ちの整理に合わせて無理のないペースで作業を進めることができ、精神的な負担を最小限に抑えながら取り組むことができます。
遺品整理に限らず、故人を失った悲しみの中で無理をするとストレスによって心身の調子を崩してしまう恐れがあり、業者のスケジュールに合わせた急いだ作業は、感情的な負担を増加させる可能性があります。



悲しみで作業が手につかない日は休んで故人を偲ぶ時間に充て、体調や気持ちが整った時に少しずつ進めるようにしましょう。
また、親族の都合に合わせて週末に集まって作業したり、平日の空いた時間に一人で進めたりと、それぞれの事情に応じた柔軟なスケジュール調整が可能です。
自分のペースを重視する場合でも、法的期限や賃貸契約の期限は守る必要があるため、全体のスケジュールを把握した上で、重要度の高い作業から優先的に進めることが大切です。
\ 24時間365日受付中 /
自分で行うデメリット


この章では、遺品整理を自分で行うデメリットについて紹介します。
自分で行うデメリットには主に以下の内容があります。
- 想像以上に必要となる時間と体力の負担
- 適切な処分方法や価値判断の困難さ
- 故人の思い出に直面することによる感情的な負担
デメリット(1)時間と体力が大幅に必要
遺品整理を自分で行う場合、想像以上に膨大な時間と労力がかかり、仕事や日常生活との両立が困難になる可能性が高く、特に遺品の量が多い場合は数ヶ月から半年以上の期間を要することもあります。
仕事で多忙な方や人手が不足している状況では、それだけ時間がかかり、遺品整理が遅々として進まず時間だけが過ぎていくのを感じると精神的にも負担が大きくのしかかります。
重い家具や家電の搬出、大量の書類の仕分け、清掃作業など体力を要する作業が連続するため、特に高齢の遺族の場合は体力的な限界もあり、無理をすると健康を害するリスクもあります。
一軒家の場合、部屋ごとの仕分け作業だけで週末を使って数ヶ月、その後の搬出・清掃作業でさらに時間を要し、平日は仕事があるため週末のみの作業となると、賃貸物件の退去期限や相続税申告期限に間に合わない可能性があります。
デメリット(2)処分方法の判断が困難
遺品整理初心者にとって、どの品物に価値があるか、適切な処分方法は何かの判断が困難で、重要な書類や貴重品を誤って処分してしまったり、逆に価値のないものを保管し続けてしまったりするリスクがあります。
遺品の中には相続手続きに必要な重要書類、資産価値のある骨董品や貴金属、デジタル遺品など、素人では価値や重要性を判断できないものが多数含まれており、これらを見落とすと相続手続きに支障をきたしたり、経済的損失を被ったりする可能性があります。



古い通帳や証券、保険証券を単なる古い書類として処分してしまったり、骨董品や美術品を粗大ゴミとして廃棄してしまったりするケースがあります。
また、パソコンやスマートフォンに保存された重要な情報の存在に気づかず、適切に処理できない場合もあります。
処分判断に迷う場合は、遺品整理士や専門の査定業者に相談することが重要です。
デメリット(3)感情的な負担が大きい
遺品整理を自分で行うことで故人の思い出と直接向き合うため、作業が進まないことに対して故人への後悔の念が強くなる遺族もおり、精神的な負担が想像以上に大きくなる可能性があります。



故人を失った悲しみの中で遺品整理を行うのは辛いことで、思い出の品を処分する罪悪感や、故人の生前の姿を思い出して感情的になってしまうことが頻繁に発生します。
故人の衣類や写真、手紙などの身の回りの品を整理する際に涙が止まらなくなったり、大切にしていた趣味の品を処分することに強い罪悪感を感じたりして、作業が手につかなくなるケースがあります。
また、親族間で思い出の品の取り扱いについて意見が分かれ、感情的な対立が生じる場合もあります。
感情的な負担を軽減するためには、無理をせずに休憩を取りながら進めること、親族で支え合いながら作業すること、どうしても辛い場合は専門のカウンセラーや業者のサポートを受けることが大切です。
\ 24時間365日受付中 /
業者依頼を検討すべき状況
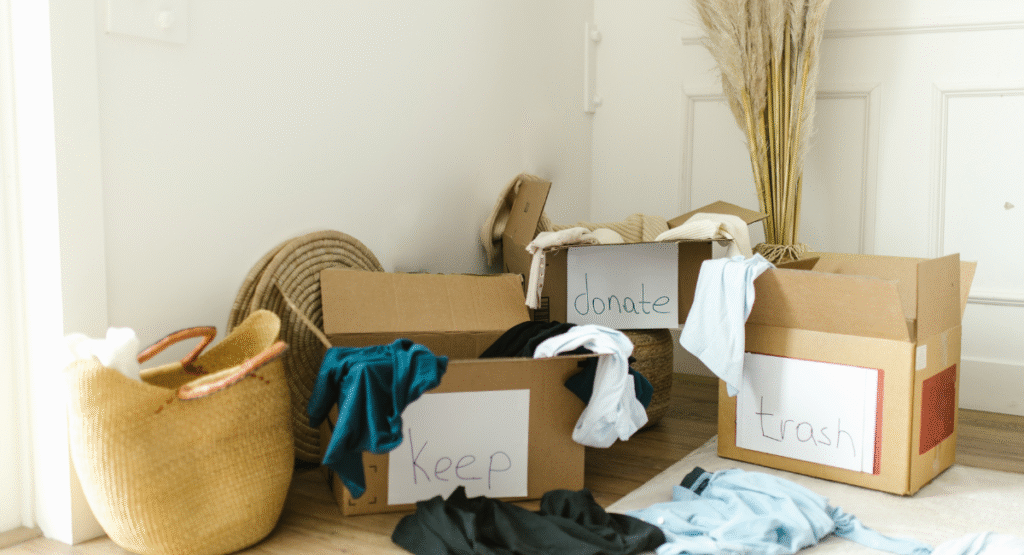
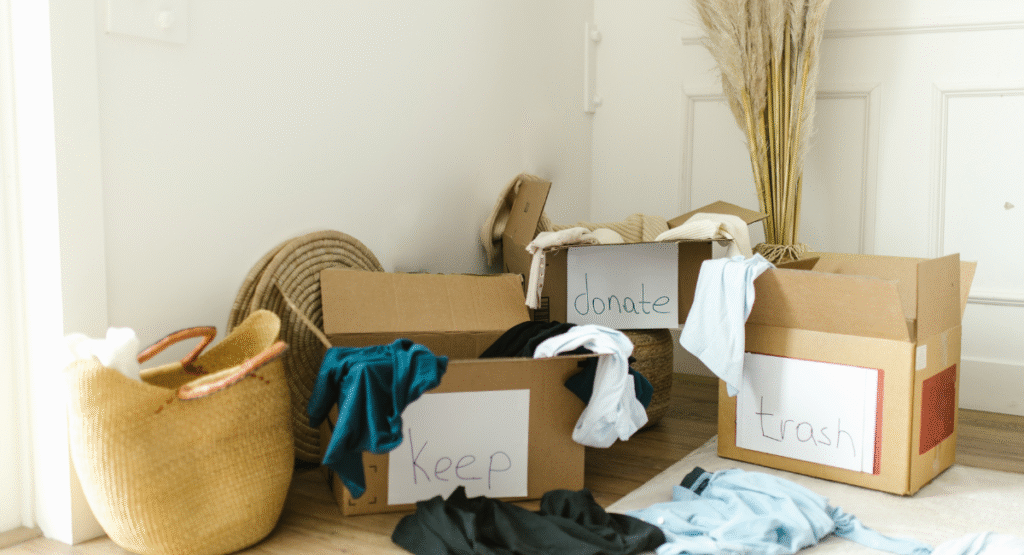
この章では、遺品整理業者への依頼を検討すべき状況について紹介します。
業者依頼を検討すべき状況には主に以下の内容があります。
- 遺品の量が膨大で短期間での処理が必要な緊急事態
- 相続人の年齢や居住地による物理的制約
- 孤独死等による特殊清掃の必要性
- 貴重品や重要書類の専門的な捜索・判断の必要性
状況(1)遺品の量が多く短期間処理が必要
賃貸物件の退去期限が1~3ヶ月と短期間に設定されており、遺品の量が膨大な場合は、自力での処理が物理的に困難なため、専門業者への依頼が必要不可欠となります。
マンションやアパートなどの部屋数の少ない賃貸物件でもおおむね1~2週間ほどの処理期間が必要で、一軒家などの場合はさらに長期間を要します。
故人がゴミ屋敷状態で生活していた場合や、長年蓄積された大量の書類・衣類・家具がある場合、自力での分類・搬出は数ヶ月を要しますが、賃貸契約では1ヶ月以内の退去を求められることが多いため、業者の機械的な処理能力が必要になります。
遺品の量を事前に把握し、退去期限から逆算して自力処理が困難と判断される場合は、早期に複数の業者から見積もりを取得し、清掃から原状回復まで一括対応できる業者を選定することが重要です。
状況(2)相続人が高齢や遠方居住
相続人が高齢で体力的に作業が困難な場合や、遠方に居住しており頻繁に作業に参加できない場合は、業者依頼が現実的な選択肢となります。
遺品整理には重い家具や家電の搬出、大量の書類の仕分け、清掃作業など体力を要する作業が連続し、高齢の遺族の場合は体力的な限界もあり、無理をすると健康を害するリスクがあります。
70代の配偶者が一人で遺品整理を行う場合や、相続人全員が故人の住居から飛行機での移動が必要な距離に住んでいる場合、物理的・経済的に自力での処理は困難です。
また、仕事や育児で多忙な相続人が多い場合も同様で、遠方居住者は交通費と時間の負担も大きくなります。



相続人の年齢・体力・居住地・生活状況を総合的に判断し、負担軽減を優先する場合は業者依頼を検討することをお勧めします。
状況(3)特殊清掃が必要
孤独死などで遺体の発見が遅れ、腐敗体液による汚損や強い臭気が発生している場合は、専用の防護服と特殊な薬剤・技術が必要なため、一般の方では対応できず、専門業者への依頼が必須となります。
人間は死後3日程度で腐敗体液が漂いはじめ、腐敗体液の臭いは窓を開けて換気、市販の芳香剤や空気清浄機を使ってもとれず、感染症のリスクもあるため、特殊清掃を依頼する必要があります。
夏場の孤独死で発見が1週間遅れた場合、床材や壁紙への腐敗体液の浸透、害虫の発生、近隣への臭気影響などが発生し、通常の清掃では対応できません。
また、賃貸物件では原状回復義務があるため、専門的な除菌・脱臭作業が必要になります。
特殊清掃が必要な場合は、遺品整理と特殊清掃を同時に行える業者を選び、経験豊富で消臭技術に力を入れている業者を選定することが重要です。
状況(4)貴重品や重要書類の捜索が困難
故人の資産状況が不明で、重要書類や貴重品の所在が分からない場合、または遺品の中に価値判断が困難な品物が多数含まれている場合は、専門知識を持つ遺品整理士への依頼が効率的です。



相続税申告や相続手続きに必要な書類の発見・整理は相続財産の把握に直結し、見落とすと正しい税額が算出できず、申告期限に間に合わない可能性があります。
また、素人では価値を判断できない骨董品や美術品を誤って処分するリスクもあります。
故人が複数の銀行口座を持っていたが詳細が不明な場合、古い株券や保険証券が混在している場合、趣味で集めていたコレクションの価値が分からない場合など、専門的な知識と経験が必要な状況です。
資産調査と遺品整理を同時に行える遺品整理士認定協会の認定業者を選び、重要書類の発見から価値査定、適切な保管・処分まで一貫してサポートを受けることで、見落としリスクを最小限に抑えることができます。
\ 24時間365日受付中 /
まとめ
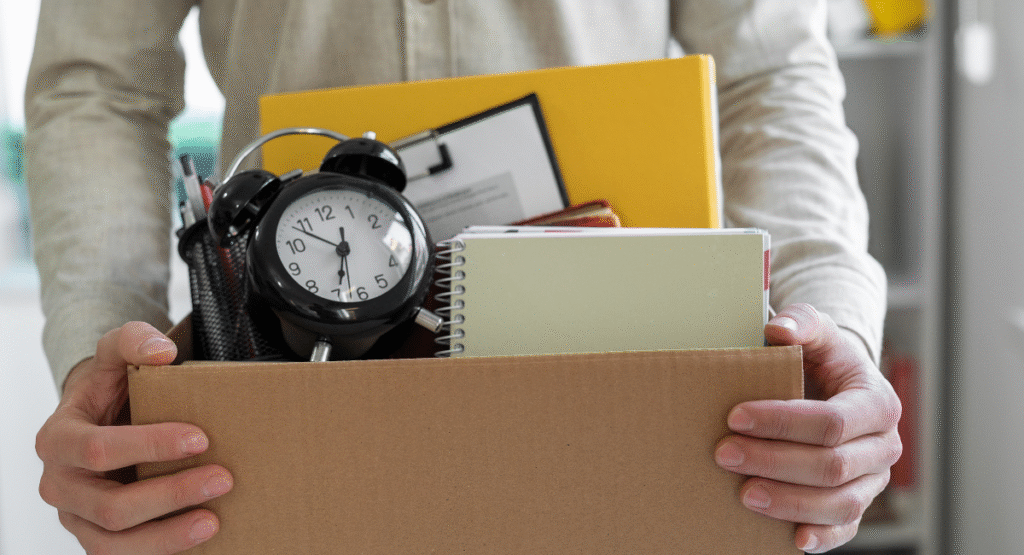
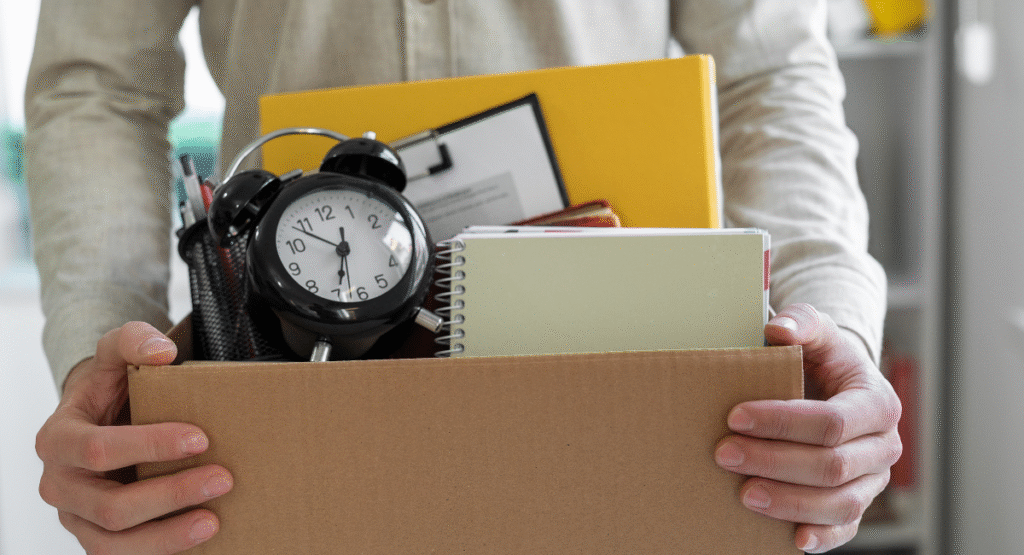
遺品整理をいつから始めるかは、住居状況と法的期限を最優先に判断することが重要です。
賃貸物件では家賃負担を避けるため葬儀直後から、持ち家では四十九日法要後を目安に開始しましょう。



相続放棄を検討する場合は3ヶ月以内、相続税申告が必要な場合は10ヶ月以内の期限を意識してください。
親族間での話し合いと役割分担を明確にし、重要書類の保管方法を決めておくことでトラブルを防げます。
自分で行う場合は費用節約と思い出を大切にできるメリットがある一方、時間と体力が必要というデメリットもあります。
遺品が多い場合や高齢・遠方の相続人がいる場合は、業者依頼も検討しましょう。