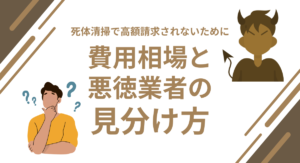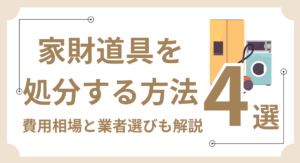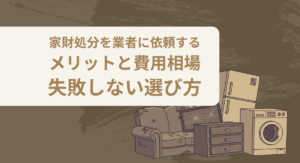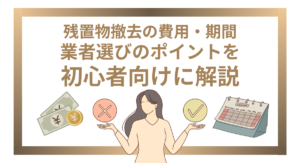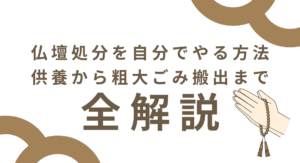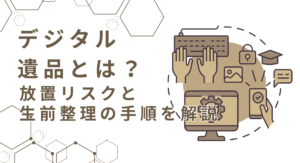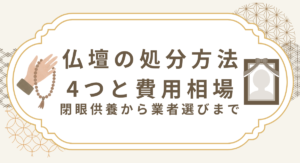生活保護受給者の死亡によるアパート退去費用の請求書が届いて、あなたは今、どうすればいいかわからず困惑していませんか?
突然の高額請求に「本当に自分が払わなければならないのか」「連帯保証人だから逃げられないのか」と不安を感じるのは当然です。
実は、多くの方が知らないまま不当な費用を支払っているケースが後を絶ちません。

相続放棄という選択肢や、大家との交渉で費用を大幅に削減できる可能性があることをご存知でしょうか?
この記事では、法的責任の境界線を明確にし、退去費用を最小限に抑える具体的な方法をわかりやすく解説します。



一人で抱え込まず、まずは正しい知識を身につけて適切な判断を行いましょう。
生活保護受給者死亡時の退去費用は誰が払う?


この章では、生活保護受給者が死亡した際のアパート退去費用の支払い責任について詳しく解説します。
突然の死亡により混乱している中でも、法的責任の所在を正確に理解することで、不当な費用請求から身を守ることができます。
- 連帯保証人の責任範囲と支払い義務の詳細
- 相続人の法的義務と相続放棄による回避方法
- 保証会社の契約内容による責任の違い
- 大家が負担すべき項目と借主負担の境界線
負担者(1)連帯保証人の責任範囲
連帯保証人は借主と同等の支払い義務を負うため、生活保護受給者の死亡後も退去費用の全額を負担する責任があります。
連帯保証人は法律上、借主と同じ責任を負う立場とされており、借主本人が死亡しても故人の債務がそのまま連帯保証人に引き継がれます。
また、相続放棄をしたとしても、賃貸借契約の連帯保証人としての原状回復義務は消えません。
連帯保証人が負担する具体的な費用
- 未払いの家賃
- 原状回復費用
- 不用品の処分代など
退去費用の全額を請求される可能性があります。



連帯保証人になる要件は基本的に支払い能力の有無だけで、親族とは限らず、友人や知人などが連帯保証人になっていることもあります。
負担者(2)相続人の法的義務
連帯保証人がいない場合や支払い能力がない場合は、相続人が退去費用を負担する法的義務があり、遺品整理も含めて相続財産として引き継がれます。
相続人は故人の一切の権利義務を承継するため、借金や税金、住居の退去費用、生活保護費に関する返還義務も承継されます。
遺品整理は遺産相続に関わる作業となるため、法律によって原則として相続人が行うと決められています。
退去費用
- 死亡後の家賃
- 動産の処分費用
- 部屋の原状回復費
特に孤独死の場合は夏場で数十万円の原状回復費を請求されることがあります。



相続放棄の手続きをすることで退去費用の支払いを回避できますが、相続の開始を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所へ申述書を提出する必要があります。
負担者(3)保証会社の契約内容
保証会社は連帯保証人の会社版として、連帯保証人がいない場合にすべての責任を負い、連帯保証人の次に責任を追う立場です。
近年は保証会社がいれば保証人なしでもOKという賃貸物件が増えており、保証会社が連帯保証人の代わりとして契約に組み込まれているケースが多いためです。
また、任意加入の保険会社については、物件のオーナーや不動産会社などが自主的に保険に入っていたら、その保険から支払いがなされます。
多くの生活保護受給者が賃貸契約時に保証会社を利用しており、保証会社のサービス内容によっては家財処分問題も解決できる場合があります。



ただし、保証範囲は契約内容により異なるため、具体的な保証内容の確認が重要です。
負担者(4)大家が負担する項目
相続人も連帯保証人も支払えない場合、最終的な費用負担者は物件の所有者である大家ですが、本来支払い義務はなく、経営上の必要性から自腹で負担するケースが多いです。
大家には法的な支払い義務はありませんが、自腹でも家財の処分などをしなければ次の入居者を入れられないため、最終的には大家が負担することになります。
残置物処分費、原状回復費、未払い家賃や空室による損失の平均を合計すると約90万円になり、家賃1年半程度の売上が吹っ飛ぶ計算になります。
大家が負担する可能性がある退去費用の項目内訳
- 残置物処分費(家財やゴミの処分など)
- 原状回復費(特殊清掃、壁紙の張り替え・床の修復など)
- 未払い家賃や空室による損失



遺品整理を業者に依頼した場合、1LDKで約8万円から、2LDKで13万円ほど、3LDKで約18万円で、孤独死の場合は原状回復費が高くなる傾向があります。
\ 24時間365日受付中 /
アパート退去費用の内訳と相場
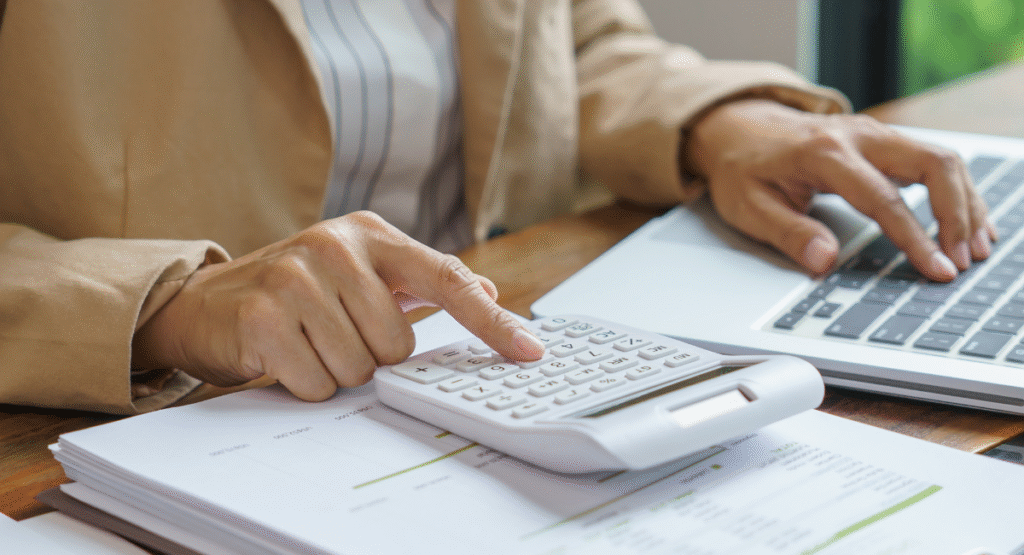
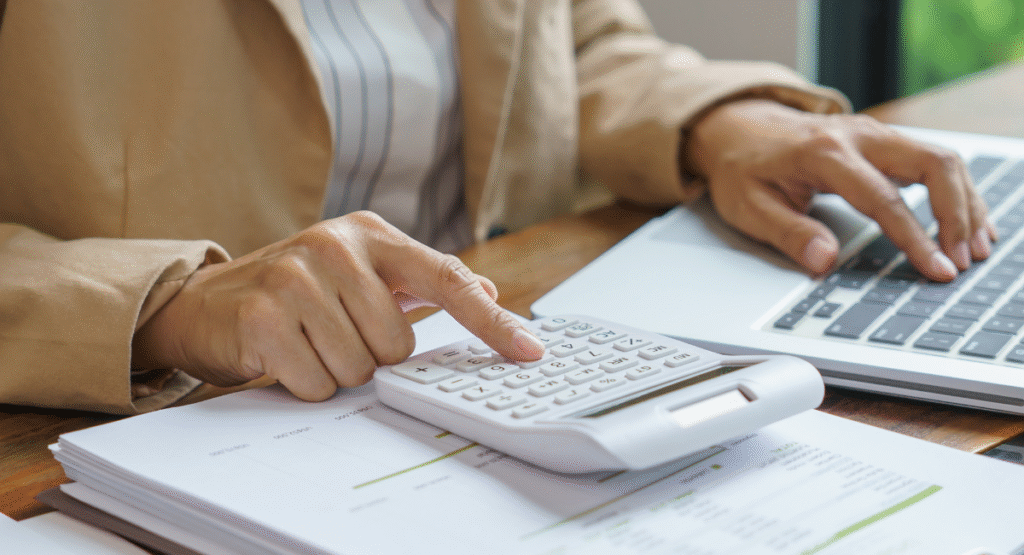
この章では、生活保護受給者が死亡した際に発生するアパート退去費用の詳細な内訳と適正相場について解説します。
正確な費用相場を把握することで、業者や大家からの不当な高額請求を見抜き、適切な交渉を行うことができます。
- 遺品整理の料金相場と作業内容による費用変動
- 特殊清掃の価格帯と発見時期による費用差
- 原状回復の適正価格と大家負担との境界線
- 家賃精算の計算方法と日割り計算のルール
費用(1)遺品整理の料金相場
遺品整理の費用相場は部屋の広さによって大きく異なり、1Kで3万円から8万円、1LDKで約8万円、2LDKで13万円程度、3LDKで約18万円が目安となります。
これらの費用には作業費を含む人件費、車両費、回収運搬費、廃棄物処分費が含まれており、処分困難物がある場合は追加料金が発生します。
生活保護受給者の場合、荷物が多く部屋の使い方が雑なケースが多いため、業者への依頼が必要になることが一般的です。
複数業者から相見積もりを取得し、価値のある遺品があれば買取サービスを活用することで費用を相殺できる可能性があります。
自分で作業を行えば費用は大幅に抑えられますが、時間と労力が必要になります。
費用(2)特殊清掃の価格帯
特殊清掃費用は遺体の発見時期によって大きく変動し、死亡から1週間以内の発見であれば10万円から30万円程度ですが、1ヶ月以上経過した場合は50万円から100万円程度が相場となります。
生活保護受給者が孤独死した場合、遺体発見まで日数が経過していることが多く、夏場では腐敗の進行により原状回復費が数十万円に達することがあります。
特殊清掃の作業内容
- 消臭・除菌作業
- 壁紙やフローリングの張替え
- エアコンなどの設備交換
遺体の腐敗により物件内の家財や壁、床に腐敗臭や体液が染みついた状態を元に戻す必要があります。
業者選定の際は産業廃棄物収集運搬許可などの必要な許可証を持つ業者を選び、過剰な清掃範囲の提案には注意が必要です。
費用(3)原状回復の適正価格
通常の退去時における原状回復費用の相場は1LDKで5万円程度ですが、物件の築年数や特殊清掃後の追加工事により費用が大幅に増加する可能性があります。
原状回復には壁紙の修復や床のクリーニング、設備の修理などが含まれ、借主の義務として物件を入居時の状態に戻すことが求められています。
ただし、通常損耗と特別損耗の区別があり、経年劣化による自然な損耗は大家負担、故意・過失による損耗は借主負担という民法の原則があります。



孤独死の場合は近隣部屋への影響による補償費が追加で発生することもあり、適正な費用かどうかを慎重に判断する必要があります。
不当な請求に対しては法的根拠を示して交渉することが重要で、大がかりな清掃が必要な場合でも専門業者への依頼により期間短縮と結果的な費用削減が可能です。
費用(4)家賃精算の計算方法
生活保護費で家賃を支払えていても、死亡時点で生活保護の支給は終了するため、死亡日から退去完了日までの家賃は別途負担する必要があります。
家賃の計算は通常、死亡が確認された日の翌日から退去手続きが完了するまでの日数で日割り計算され、例えば月額5万円のアパートで退去まで2ヶ月かかった場合は10万円の家賃が発生します。
遺品整理や原状回復まで時間がかかるほど退去が遅くなり家賃負担が増加するため、アパートの間取りが小さい場合は作業量が少なく短期間で終わらせることができます。
費用負担を最小限に抑えるためには早期の退去作業開始が重要で、ライフライン(電気・ガス・水道)や駐車場契約の解約手続きも速やかに行う必要があります。



業者に依頼する場合も作業期間の短縮を重視した業者選定が効果的です。
\ 24時間365日受付中 /
生活保護費の返還義務と債務処理


この章では、生活保護受給者が死亡した際に発生する生活保護費の返還義務と、その他の債務との関係について解説します。
相続人が突然直面する複雑な債務問題を整理し、適切な対処法を選択できるよう支援します。
- 不正受給による返還義務の範囲と相続への影響
- 生活保護費返還と借金の優先順位の法的根拠
- 債務整理や相続放棄による負担軽減の方法
返還(1)不正受給による義務範囲
生活保護受給者が不正受給していた場合、相続人に返還義務が課されることがあり、生活保護法第78条により費用の全部または一部と140%以下の加算金が徴収される可能性があります。
相続人は故人の一切の権利義務を承継するため、生活保護費の受給権は相続されませんが、借金や税金、生活保護費に関する返還義務は承継されます。



実際に司法書士事務所に来られた相続人の中には、生活保護費の返還を知らせる書面で死亡を知った人もいます。
不実の申請その他不正な手段により保護を受けた場合は、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長が、その費用の額の全部又は一部を徴収するほか、その徴収する額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収することができます。
生活保護費の返還義務があるかわからない場合は、まず福祉事務所に問い合わせて正確な状況を把握することが重要です。
返還(2)借金との優先順位
生活保護費の返還義務と一般的な借金は同等の債務として扱われ、特別な優先順位はありませんが、相続人はこれらすべての債務を承継することになります。
相続において、現金預金や不動産などのプラスの財産だけでなく、故人が背負っていた借金などの負の遺産も含まれており、相続人はそれもすべて相続することになります。
プラスの財産だけ相続して、マイナスの財産は放棄するということは、絶対にできません。



借金や返還義務以外にも、退去費用や税金滞納分を請求されることもあり、例えば現預金が100万円あったとしても、借金が300万円あったら、差し引き200万円のマイナス相続になります。
生活保護受給者の場合、プラスの財産がほとんどないケースが多いため、借金と生活保護費返還義務の合計額を正確に把握し、マイナス相続になる場合は相続放棄を検討することが重要です。
返還(3)債務整理による軽減
相続放棄は相続を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きする必要があり、これにより生活保護費返還義務を含むすべての債務から解放されます。



相続放棄をすると負債から逃れられますが、遺産も相続できないため、相続放棄の申請には期限があり、遺品整理をすると相続の意思があるとみなされ、相続放棄できなくなる場合があります。
当事務所で依頼を受けた相続放棄でも、生活保護を受給している兄弟だけ相続放棄しなかったケースがあります。
これは借金を相続しても差し押さえられる財産が無いので、借金が増えても生活に影響がないからです。
口座凍結前に返還金や生活資金を引き出すと相続放棄ができなくなる場合があるため注意が必要です。
債務整理の選択肢としては相続放棄が最も効果的ですが、3ヶ月の期限内に手続きを完了する必要があり、複雑な債務関係では専門家への相談が重要です。
\ 24時間365日受付中 /
相続放棄のメリット


この章では、生活保護受給者の死亡に伴う相続放棄のメリットについて詳しく解説します。
相続放棄は高額な退去費用や債務から逃れる有効な手段であり、適切に活用することで経済的負担を大幅に軽減できます。
- 退去費用の免責効果と法的根拠
- 債務からの完全解放による経済的メリット
- 生活保護費返還義務の回避方法
メリット(1)退去費用の免責効果
相続放棄の手続きをすることで退去費用の支払いを回避でき、相続の開始を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所へ申述書を提出すれば、高額なアパート退去費用から完全に解放されます。
相続人は通常であれば故人の一切の権利義務を承継するため退去費用も相続財産として引き継がれますが、相続放棄により相続人ではなくなるため、これらの費用負担義務も消滅します。



実際に原状回復費が高すぎるので相続放棄を決めた相続人もおり、退去費用が数十万円から100万円以上になる可能性がある孤独死のケースでは、相続放棄により大幅な費用削減効果が期待できます。
ただし、遺品整理をすると相続の意思があるとみなされ、相続放棄できなくなる場合があるため、遺品に手を付ける前に司法書士や弁護士に相談することが重要です。
メリット(2)債務からの完全解放
相続放棄により、故人の借金や税金滞納分、医療費など、すべての債務から完全に解放され、相続人として追徴金ともども請求されることを回避できます。
生活保護受給者の場合、相続対象となるのは以下のような財産です。
- 現金・預金・不動産などのプラスの財産
- 故人が背負っていた借金・税金滞納分などのマイナスの財産
債務総額がプラス財産を上回る場合は相続放棄が有効です。
例えば現預金が100万円あったとしても、借金が300万円あったら差し引き200万円のマイナス相続になります。



生活保護受給者の場合、プラスの財産がほとんどないケースが多いため、総債務額を正確に把握すれば、相続放棄により大幅な負担軽減が可能です。
故人の全ての債務を調査し、プラス財産との差額を計算してマイナス相続になる場合は迷わず相続放棄を選択することが重要です。
メリット(3)返還義務の回避
相続放棄により、生活保護費の返還義務からも解放され、不正受給による140%以下の加算金を含む返還請求を回避できます。
相続人は故人の借金や税金、生活保護費に関する返還義務も承継するため、生活保護法第78条による返還義務が発生していた場合、相続人に高額な返還請求が行われる可能性があります。
実際に司法書士事務所に来られた相続人の中には、生活保護費の返還を知らせる書面で死亡を知った人もいます。
不正受給の場合、本来の返還額に加えて40%以下の加算金も請求される可能性があり、相続放棄により数百万円の負担を回避できるケースもあります。
返還義務に後から気付いても、死亡当時に気付くのが困難であれば相続放棄が可能な場合があります。



生活保護費の返還義務の有無が不明な場合は、まず福祉事務所に問い合わせて正確な状況を把握することが重要です。
\ 24時間365日受付中 /
相続放棄のデメリット


この章では、相続放棄を選択する際に理解しておくべきデメリットについて詳しく解説します。
相続放棄には大きなメリットがある一方で、重要な制約やリスクも存在するため、慎重な判断が必要です。
- プラス財産も同時に放棄することによる機会損失
- 手続き期限の制約と期限管理の重要性
- 取り消し不可のリスクと後悔を避ける判断基準
デメリット(1)プラス財産も放棄
相続放棄をすると負債から逃れられますが、遺産も相続できないため、故人に価値のある財産があった場合、それらも同時に放棄することになります。
プラスの財産だけ相続して、マイナスの財産は放棄するということは絶対にできません。
相続放棄は全て受け取らないという選択であり、部分的な相続や選択的な放棄は法的に認められていません。



生活保護受給者でも預金や保険金、貴重品などのプラス財産が存在する可能性があります。
故人が生命保険に加入していた場合や、価値のある骨董品、貴金属を所有していた場合、これらの財産価値が債務を上回る可能性もあります。
また、生活保護受給者でも少額の預金や、親族からの贈与品などが残されているケースがあるため、事前に被相続人の財産・債務をすべて洗い出して判断することが重要です。
デメリット(2)手続き期限の制約
相続放棄には相続権があることを知ってから3か月以内というタイムリミットがあり、よほどの事情がなければ、3か月を過ぎると相続を放棄する手続きは認められません。



このタイムリミットの起点はあくまでも相続人であることを知ってからであり、誰かからの連絡によって相続人になったことを知ったときから計算が始まります。
実際に司法書士事務所に来られた相続人の中には、生活保護費の返還を知らせる書面で死亡を知った人もいます。
このような場合は書面を受け取った日から3ヶ月以内に家庭裁判所での手続きを完了させる必要があります。
遺品整理や債務調査に時間をかけすぎると期限を過ぎてしまう危険性があるため、相続人であることを知った時点で直ちに司法書士や弁護士に相談し、3ヶ月の期限を意識したスケジュール管理を行うことが重要です。
デメリット(3)取り消し不可のリスク
相続放棄は一度家庭裁判所で受理されると取り消すことができず、後から価値のある財産が発見されても、それを相続することはできません。
相続放棄は法的効力が確定的であり、後から状況が変わっても撤回や変更ができない不可逆的な手続きだからです。
相続放棄後に故人の銀行口座から多額の預金が発見されたり、不動産の価値が債務を大幅に上回ることが判明したりしても、一度放棄した相続権を回復することはできません。
また、口座凍結前に返還金や生活資金を引き出すと相続放棄ができなくなる場合があり、このような単純承認とみなされる行為にも注意が必要です。



遺品整理をすると相続の意思があるとみなされ、相続放棄できなくなる場合もあるため、相続放棄の決定前に可能な限り故人の財産状況を詳細に調査し、専門家のアドバイスを受けながら慎重に判断することが重要です。
\ 24時間365日受付中 /
退去費用を抑える実践方法


この章では、生活保護受給者の死亡に伴うアパート退去費用を効果的に抑制する具体的な方法について解説します。
適切な知識と交渉術を身に付けることで、大幅な費用削減を実現できる可能性があります。
- 複数業者の見積もり比較による適正価格の把握
- 大家との減額交渉術と法的根拠の活用
- 遺品売却による費用補填の効果的な方法
- 不要項目の見分け方と請求内容の精査
方法(1)複数業者の見積もり比較
複数の業者から見積書をもらって比較することが重要で、特に故人が生活保護受給者の場合、安い業者を選定したことの証拠としても見積書が必要です。
業者によって金額や対応している業務内容が異なり、業者間での価格差は大きく、同じ作業内容でも数十万円の差が生じることがあります。
遺品整理業者の相場
- 1Kで3万円から8万円
- 2LDKで13万円程度



業者によっては同じ作業で倍以上の見積もりを提示する場合があります。
悪質業者の見分け方として、飛び込み営業や異常な高額請求をする業者には注意が必要です。
最低3社以上の業者から詳細な見積もりを取得し、作業内容の内訳と料金体系を慎重に比較することで適正価格を把握でき、急いでいても即決せず、必ず複数の選択肢を検討してから業者を決定することが重要です。
方法(2)大家との減額交渉術
アパートの退去費用については、相続人と家主の間で金額を協議することができ、家主の中にはやむを得ない事情だからと、退去費用を安く済ませてくれる人もいます。
民法の原状回復義務において、通常損耗は大家負担、故意・過失による損耗は借主負担という原則があり、すべてが借主負担になるわけではありません。
通常損耗である自然な劣化は大家負担であることを根拠に、壁紙の一部張替えや設備の経年劣化部分については負担軽減を求めることができます。
連帯保証人や相続人の中には、どうしても退去費用を支払えない方もいるため、事情を説明することで理解を得られる場合があり、分割払いの相談も有効な交渉材料となります。
大家との交渉では、民法の原状回復ルールを理解し、経済的困窮の事情を誠実に説明することが重要で、一括払いが困難な場合は分割払いの提案も行い、双方が納得できる解決策を模索しましょう。
方法(3)遺品売却による費用補填
価値のある遺品があれば買取サービスを活用して費用を相殺することも検討でき、遺品の中から現金化できるものを見つける方法と売却手順を活用することで退去費用の負担を軽減できます。
生活保護受給者でも貴金属、骨董品、家電製品、ブランド品などの価値のある物品を所有している可能性があり、これらを適切に査定・売却することで、退去費用の一部または全部を補填できます。
売却対象になるもの
- 貴金属(指輪、ネックレス)
- 時計
- 家電製品(冷蔵庫、洗濯機)
- 家具(アンティーク品)
- 書籍(初版本、専門書)



リサイクルショップでの買取とネット売却を使い分け、複数の査定を受けることで最高値での売却が可能です。
ただし、遺品整理をすると相続の意思があるとみなされ、相続放棄できなくなる場合があるため、相続放棄を検討している場合は注意が必要です。
方法(4)不要項目の見分け方
退去費用の見積もりには不当な項目や過剰な作業が含まれている場合があり、適正な費用項目を見分けることで大幅な費用削減が可能です。
特殊清掃業者選択の注意点として、過剰な清掃範囲の提案には注意が必要であり、業者によっては不要な追加作業を提案してくる場合があります。
不要な項目
- 過剰な特殊清掃範囲(影響のない部屋まで含める)
- 高額な消臭剤の使用
- 不必要な設備交換
- 処分不要な家具の撤去費用
ゴミ屋敷清掃や特殊清掃が必要な現場の場合、料金が大きく変わるため、本当に必要な作業かどうかの見極めが重要です。



見積書の各項目について詳細な説明を求め、作業の必要性を確認することが大切です。
見積書の全項目について作業の必要性と料金の妥当性を確認し、不明な点は遠慮なく質問することが重要です。
\ 24時間365日受付中 /
死亡から退去完了までの手続き


この章では、生活保護受給者の死亡から退去完了までに必要な手続きの流れと優先順位について解説します。
複雑な手続きを時系列で整理することで、限られた時間の中で効率的に対応できるよう支援します。
- 死亡届とケースワーカー連絡の緊急手続き
- 賃貸契約の解除手続きと期限管理
- 専門窓口への相談とサポート体制の活用
- 必要書類の準備方法と入手先の案内
手順(1)死亡届とケースワーカー連絡
死亡届は故人が亡くなったことを7日以内に市区町村へ届け出る必要があり、この届出により戸籍に死亡の記載がなされ、住民票も消除されます。
同時に、生活保護受給者が亡くなったら、まずケースワーカーか役所の福祉係に連絡をしておく必要があります。



死亡届は医師が記入する死亡診断書と一体となっていることが一般的で、病院で受け取った診断書をそのまま役所へ提出する流れです。
届出先は以下のいずれかの市区町村役場
- 死亡地
- 本籍地
- 届出人の住所地
(※手数料はかかりません。)
ケースワーカーへの連絡では、生活保護費の精算、医療費の処理、今後の手続きについて具体的な指導を受けることができ、この段階で相続放棄の検討についてもアドバイスを得られる場合があります。
死亡発覚から24時間以内に死亡届の提出とケースワーカーへの連絡を完了させることが重要です。
手順(2)賃貸契約の解除手続き
賃貸契約の解除手続きは早期に行うことが重要で、早い時期に解約手続きを行うことで退去日までにかかる家賃を最小限に抑えられます。



生活保護費で家賃を支払えていても、死亡時点で生活保護は終了し、死亡後の家賃は生活保護費で支払うことができないため、解約が遅れるほど家賃負担が増加します。
解約手続きでは、以下の確認が必要です。
- 賃貸借契約書の確認
- 連帯保証人の確認
- 敷金の取り扱い
- 退去予定日の設定
ライフラインや駐車場などの解約も早期に行うことで、無駄な出費を防げます。
大家との交渉では、生活保護受給者の突然の死亡という事情を説明し、分割払いや減額の可能性を探ることが重要で、死亡確認から1週間以内に大家または管理会社に連絡し、解約手続きと退去条件の協議を開始する必要があります。
手順(3)専門窓口への相談
市区町村の法律相談、法テラスの利用、生活困窮者支援センターなど、無料相談できる機関を活用することで、専門的なアドバイスを受けながら適切な判断ができます。
生活保護受給者の死亡に伴う法的問題は複雑で、相続放棄、債務整理、退去費用の責任範囲など、専門知識が必要な判断が多数発生するためです。
司法書士・弁護士費用の目安
- 司法書士への相続放棄依頼の費用は3万円から5万円
- 弁護士への交渉依頼は着手金10万円から30万円程度
- 初回相談は無料の場合が多い
法テラスでは収入要件を満たせば弁護士費用の立替制度も利用でき、生活保護担当課、福祉事務所、地域包括支援センターでも関連する相談を受け付けています。
まず無料相談を活用して全体的な状況を把握し、必要に応じて有料の専門家に依頼する段階的なアプローチが効果的です。
手順(4)必要書類の準備方法
相続放棄、退去手続き、各種解約に必要な書類を事前に準備することで、手続きの遅延を防ぎ、期限内での対応を確実にできます。
相続放棄には3ヶ月以内という厳格な期限があり、必要書類の準備不足により手続きが遅れると、相続放棄ができなくなるリスクがあります。
相続放棄に必要な書類
- 相続放棄申述書
- 故人の住民票除票
- 戸籍謄本
- 申述人の戸籍謄本
退去手続きに必要な書類
- 賃貸借契約書
- 死亡診断書のコピー
- 相続関係を示す書類
その他各種解約に必要な書類
- 身分証明書
- 印鑑証明書
書類の入手先は市区町村役場、法務局、契約先企業などで、必要書類のチェックリストを作成し、入手先と手数料を事前に確認して効率的に収集することが重要です。



相続放棄関連の書類は家庭裁判所のウェブサイトからダウンロードできます。
\ 24時間365日受付中 /
まとめ
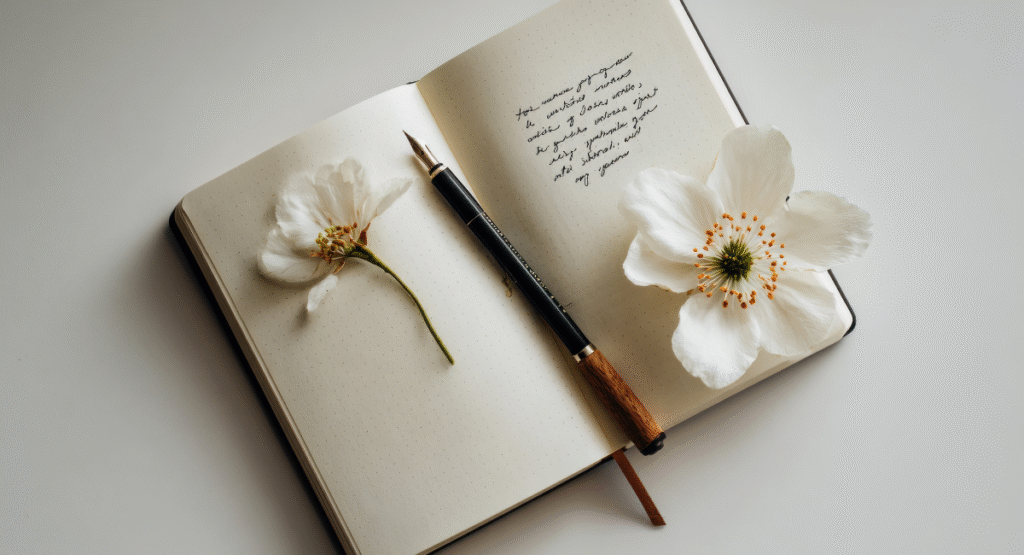
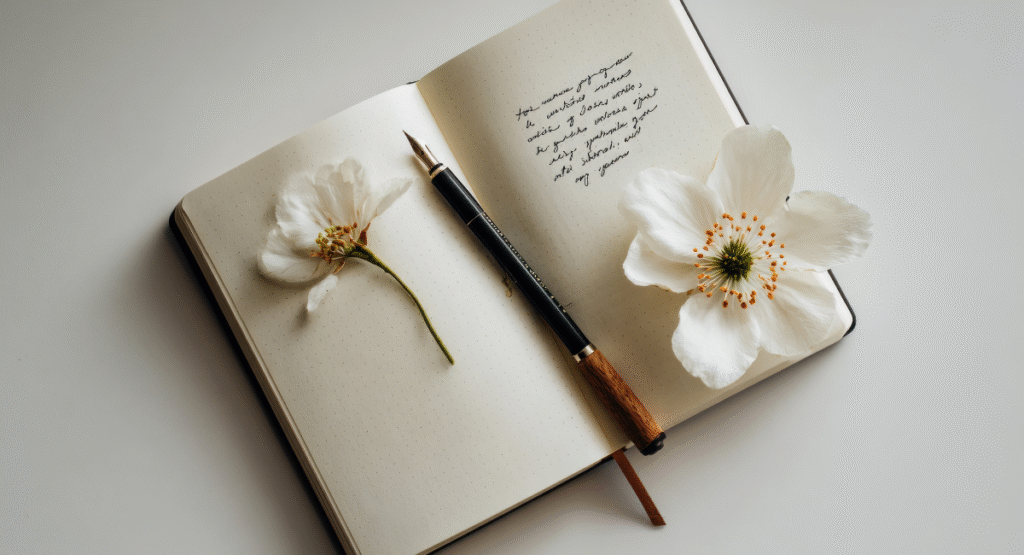
生活保護受給者の死亡によるアパート退去費用は、相続人や連帯保証人に大きな経済的負担となりますが、適切な知識と対処法で負担を大幅に軽減できます。
最も重要なのは相続放棄という選択肢で、死亡から3ヶ月以内に手続きすれば退去費用を含む全ての債務から完全に解放されます。
相続する場合でも、複数業者からの見積もり比較や大家との減額交渉により費用を抑制可能です。
まずは自分の法的責任範囲を正確に把握し、ケースワーカーや法律相談窓口への相談を通じて、経済状況に応じた最適な解決策を迅速に判断することが重要です。