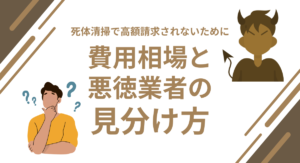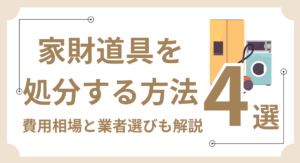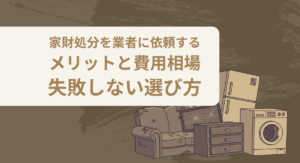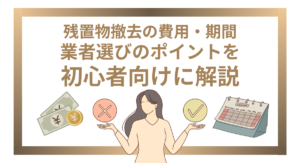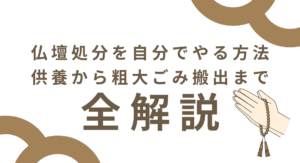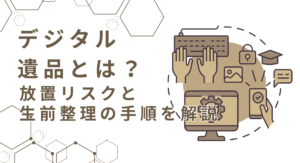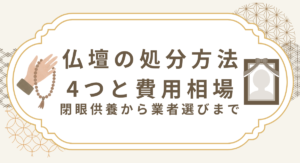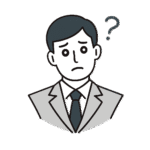
遺品整理で絶対に捨ててはいけないものを把握せずに作業を始めて、後から「あの書類が必要だった」と後悔したことはありませんか?
大切な家族を亡くした悲しみの中で進める遺品整理は、感情的な判断になりがちで、重要な遺言書や通帳、デジタル遺品を見落とすリスクが潜んでいます。
相続手続きの期限が迫る中、親族間のトラブルを避けながら安全に進めるには、明確な判断基準とチェックリストが欠かせません。
この記事では、法的トラブルを回避し、故人の思いを大切にしながら効率的に遺品整理を完了させる具体的な方法をお伝えします。
遺品整理で捨ててはいけないもの一覧


この章では、遺品整理を行う際に絶対に捨ててはいけないものについて詳しく紹介します。
これらのアイテムは主に以下のような理由で重要性が高く、処分すると取り返しのつかない事態になる可能性があります。
- 法的手続きで必要となる重要書類や財産関連の品々
- 相続や税務手続きに直接関わるもの
- 親族間のトラブルを避けるために保管すべきもの
- デジタル化が進む現代において見落としがちなデジタル遺品
(1)遺言書・エンディングノート
遺言書とエンディングノートは、遺品整理において最も重要な書類であり、絶対に処分してはいけません。
遺言書は法的拘束力を持つ故人の最後の意思表示であり、相続の進め方を大きく左右する重要な文書です。
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のいずれも発見した場合は、公正証書遺言以外は家庭裁判所での検認手続きが必要になります。



エンディングノートには法的拘束力はありませんが、故人の希望や重要な情報、銀行口座情報、保険契約、デジタルサービスのパスワードなどが記載されている場合があり、遺族にとって貴重な指針となります。
発見次第、他の相続人全員に報告し、専門家に相談することが重要です。
(2)現金・へそくり・金庫の中身
現金や貴重品が保管されている可能性のある金庫類は、必ず中身を確認してから処分を検討する必要があります。
故人が現金を自宅で保管していることは珍しくなく、タンス預金やへそくりとして相当額の現金が見つかることがあります。
これらは相続財産として申告が必要で、見落とすと相続税の申告漏れとなり、被相続人の死亡日の翌日から10ヶ月以内という期限内に適切に処理する必要があります。
仏壇の中、本の間、衣類の間、家具の引き出しの奥、押し入れの天袋など意外な場所に現金が隠されている場合があります。
金庫には遺言書や重要書類、貴金属なども入っている可能性が高いため、専門業者による開錠も検討しましょう。
(3)通帳・キャッシュカード・印鑑
金融機関関連の品々は相続手続きに直結するため、絶対に処分してはいけません。
通帳には故人の財産状況が記録されており、相続税申告や遺産分割の基礎資料となります。
印鑑は銀行手続きや各種契約の解除に必要で、ネット銀行の存在確認や定期預金、投資信託などの金融商品の把握にも重要な手がかりとなります。
銀行の普通預金・定期預金通帳、ゆうちょ銀行の通帳、信用金庫の通帳、証券会社の取引明細、実印・銀行印、キャッシュカード、クレジットカードなどが対象です。



最近では紙の通帳を発行しないネット銀行も多いため、スマートフォンやパソコンでの確認も必要になります。
すべての金融機関に連絡を取り、口座の残高証明書を取得することが重要です。
(4)有価証券・保険証券・投資関連書類
株券、債券、保険証券、投資信託などの金融商品関連書類は、高額な相続財産である可能性が高いため絶対に保管してください。
これらは相続税の課税対象となる重要な財産で、特に株式や投資信託は市場価格の変動があるため、相続開始時点での正確な評価が必要です。
生命保険は受取人によって相続財産かどうかが決まり、相続税の非課税枠もあるため専門的な知識が必要になります。
上場株式の株券、国債・社債、投資信託の取引報告書、生命保険証券、火災保険証券、自動車保険証券、年金保険の証券、外貨預金の明細、証券会社からの取引残高報告書などが該当します。
各証券会社や保険会社に連絡を取り、現在の残高や契約内容を確認することが重要です。
(5)身分証明書・年金手帳・健康保険証
身分証明書類は各種手続きの基礎となるため、返却手続きが完了するまで保管が必要です。
健康保険については故人の住所地の役所の担当窓口に資格喪失届を提出し、健康保険証を返却する必要があります。
老齢基礎年金や老齢厚生年金を受給していた場合は、最寄りの年金事務所または年金相談センターで受給停止の手続きを行います。
これらの手続きは死亡後14日以内という期限があるため注意が必要です。
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、健康保険証、年金手帳、介護保険証、身体障害者手帳、各種資格証明書などが対象となり、本人確認や各種手続きに必要となる場合があります。
返却が必要なものは速やかに各窓口で手続きを行いましょう。
(6)不動産関連書類・契約書
不動産関連書類は相続登記や財産評価に必須のため、絶対に処分してはいけません。
2024年度からは相続登記の義務化がスタートし、相続登記は相続開始から3年以内に行うことが義務化され、違反すると過料が課される可能性があります。
不動産は相続財産の中でも高額になることが多く、正確な評価と適切な手続きが必要です。
土地・建物の権利証(登記済証・登記識別情報)、固定資産税納税通知書、不動産売買契約書、住宅ローンの契約書、賃貸借契約書、測量図、建築確認済証などが該当します。
法務局で登記簿謄本を取得し、故人名義の不動産をすべて把握することが重要です。
相続登記の手続きには司法書士への相談をお勧めします。
(7)仕事関係の資料・借用書
仕事関係の契約書や借用書は、債権債務の把握に重要なため慎重に確認してください。
故人が事業を営んでいた場合や個人間の金銭貸借がある場合、これらは相続財産として申告が必要です。
また事業承継や債務整理が必要な場合もあります。
借金がある場合は、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に相続放棄や限定承認の手続きを検討する必要があります。
個人事業の帳簿、契約書、請求書、領収書、借用書、連帯保証契約書、リース契約書、業務委託契約書などが対象となります。



特に借用書や保証契約書は将来の債務につながる可能性があるため、すべての契約関係を整理し債権債務を明確にすることが重要です。
(8)デジタル遺品・スマホ・パソコン
デジタル遺品とは、パソコンやスマホなどのデジタル機器に保存されたデータやインターネットサービスのアカウント等を指します。
スマートフォンでインターネットを利用する人は、20〜59歳の各年齢層で約9割、60代で78.3%、70代が49.4%となっており、現代では重要な遺品となっています。
デジタル遺品は思い出の写真や動画などのデータを取り出すだけでなく、家族に黙って株式やFXの取引をしていたり借り入れがあったりする場合、そのまま放置していると為替変動による損の発生や金利が増えてしまう金銭的被害が発生する可能性があります。
スマートフォン、パソコン、タブレット、外付けハードディスク、USBメモリ、SNSアカウント、ネット銀行のアカウント、暗号資産、オンライン証券口座、各種サブスクリプション契約などが該当します。
(9)レンタル品・リース品
レンタル・リース契約品は返却義務があるため、契約内容を確認して適切に処理する必要があります。
故人名義のレンタル品やリース品をそのまま放置すると、継続的に料金が発生し、最終的に相続人が支払い義務を負うことになります。
また契約違反により損害賠償を請求される可能性もあります。
福祉用具(車椅子、介護ベッド等)、医療機器(酸素濃縮器、人工呼吸器等)、通信機器(ポケットWi-Fi、固定電話等)、自動車リース、パソコンリース、コピー機リースなどが対象です。



契約書を確認して貸出先に連絡し、返却手続きを速やかに行う必要があります。
返却に費用がかかる場合もあるため、契約内容をよく確認することが重要です。
(10)鍵類・支払通知書
各種の鍵と継続的な支払いに関する通知書は、財産把握と債務整理のために重要です。
鍵類は故人が所有していた財産(不動産、自動車、金庫、ロッカー等)へのアクセスに必要で、これらの財産の存在確認に重要な役割を果たします。
支払通知書は継続的な債務を把握し、不要な支払いを停止するために必要です。
家の鍵、自動車の鍵、金庫の鍵、ロッカーの鍵、電気・ガス・水道の検針票や請求書、携帯電話の料金明細、インターネット回線の請求書、各種保険料の支払通知書、税金の納付書などが該当します。
すべての鍵の用途を確認し、継続的な支払いは必要性を検討して不要なものは解約手続きを行ってください。



公共料金は名義変更や停止の手続きが必要になります。
(11)貴金属・骨董品・美術品
価値のある可能性がある品物は、専門家による鑑定を受けるまで処分を控えてください。
骨董品、貴重品や現金などが見つかった場合、相続税の申告が必要になる場合があります。
遺品整理の過程で発見された財産は、正しく評価し相続財産に含める必要があるため、素人判断での処分は禁物です。
金・銀・プラチナ製品、宝石、腕時計(高級ブランド)、絵画、掛け軸、陶磁器、茶道具、書籍(古書)、切手、古銭、刀剣類などが該当します。
見た目では価値が分からないものでも、実は高価な品物である場合があります。
まずは写真を撮影して記録を残し、美術品商や古物商などの専門家に鑑定を依頼してください。
価値が判明してから処分方法を検討することが重要です。
(12)写真・手紙・思い出の品
故人との思い出が詰まった品々は、家族間で十分に話し合ってから処分を決めてください。
これらの品々には経済的価値はないかもしれませんが、家族や親族にとって替えの利かない精神的価値があります。
一度処分してしまうと二度と取り戻すことができないため、慎重な判断が必要です。
また写真や手紙には重要な情報が含まれている場合もあります。
家族写真、アルバム、卒業証書、表彰状、手紙、日記、年賀状、故人の作品、趣味のコレクション、子どもの頃の作品、旅行の記念品などが該当します。
親族全員で話し合い、分配方法や保管方法を決めてください。



大量にある場合はデジタル化してデータとして保存することで、場所を取らずに思い出を残すことができます。
\ 24時間365日受付中 /
遺品整理を始める適切なタイミング
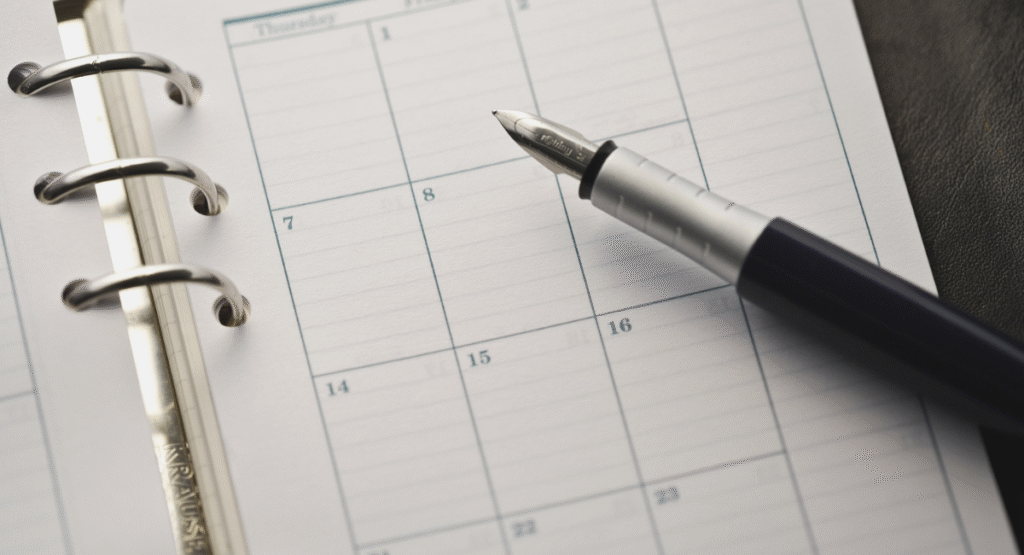
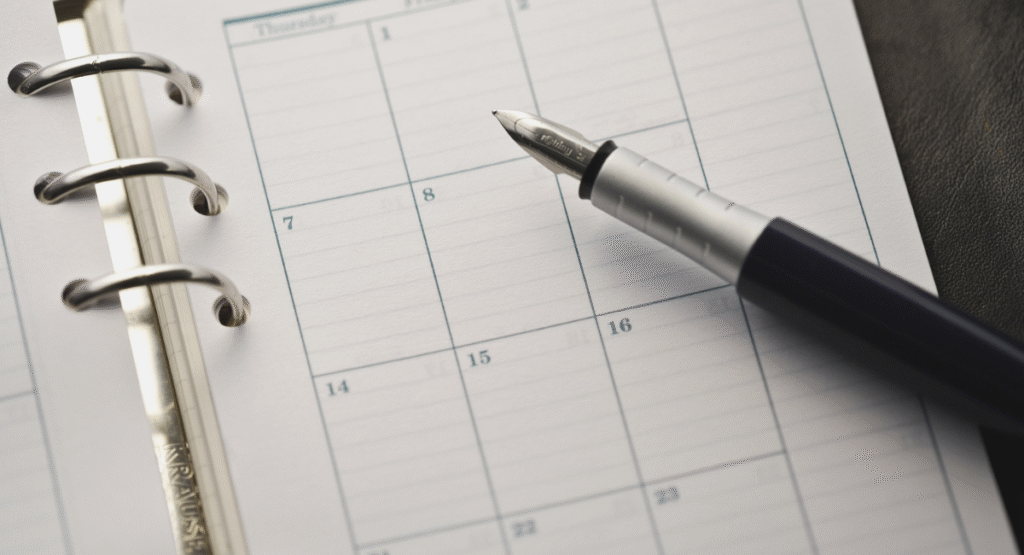
この章では、遺品整理を開始する最適なタイミングについて紹介します。
遺品整理のタイミングには主に以下の内容があります。
- 法要や親族が集まる機会を活用したタイミング
- 各種相続手続きの期限を考慮したスケジュール調整
- 賃貸契約や施設退去など物理的な制約からの逆算
タイミング(1)四十九日法要前後
四十九日法要の前後は、遺品整理を開始する最も一般的で適切なタイミングとされています。
この時期は親族が集まりやすく、遺品整理や形見分けについて相談しやすい環境が整います。



故人が成仏できるように丁寧に弔う期間として位置づけられており、遺品整理を通じて故人を偲ぶ意味でも適切です。
法要後は忌明けとなり、魂があの世へ行くという区切りになるため、心理的にも整理を始めやすいタイミングといえます。
一般的に故人が亡くなってから49日目に四十九日法要が行われ、この機会に遠方に住む親族も集まることが多くなります。
法要の際に遺品整理の進め方や役割分担について話し合い、相続人全員で納得のいく形見分けを行うことができるでしょう。
タイミング(2)相続手続きとの兼ね合い
相続放棄の期限である3ヶ月以内と相続税申告期限である10ヶ月以内を考慮して、遺品整理のスケジュールを立てることが重要です。
相続放棄や限定承認は相続開始から3ヶ月以内に決定する必要があり、この判断には故人の財産と債務の全体像を把握することが不可欠となります。
相続税の申告期限は被相続人の死亡日の翌日から10ヶ月以内と定められており、相続財産の評価には遺品整理で発見される財産も含まれます。
2024年度から相続登記が義務化され、相続開始から3年以内の手続きが必要になったことも重要なポイントです。
故人に借金がある可能性がある場合は早期に財産調査を兼ねた遺品整理が必要で、相続税申告が必要な場合は骨董品や美術品などの鑑定に時間がかかることを考慮してスケジュールを組む必要があります。
タイミング(3)賃貸契約期限から逆算
故人が賃貸住宅に住んでいた場合や施設に入所していた場合は、契約期限から逆算して遺品整理のスケジュールを組む必要があります。
賃貸住宅の場合、故人の死亡後も賃貸借契約は継続するため、家賃が発生し続けることになります。
多くの施設では「死亡後1週間以内に退所」などのルールが定められており、これらの期限に間に合わせるためには迅速な対応が必要です。
期限を過ぎると経済的な負担が増加するだけでなく、他の入居希望者に迷惑をかける可能性もあります。
賃貸マンションの場合は月末までに退去すれば翌月の家賃は不要になることが多いため、契約内容を確認して効率的なスケジュールを立てることが大切です。
遠方に住んでいる場合は親族で協力して短期間で作業を完了させる計画を立て、必要に応じて遺品整理業者への依頼も検討することをお勧めします。
\ 24時間365日受付中 /
重要なものを処分した場合の対処法
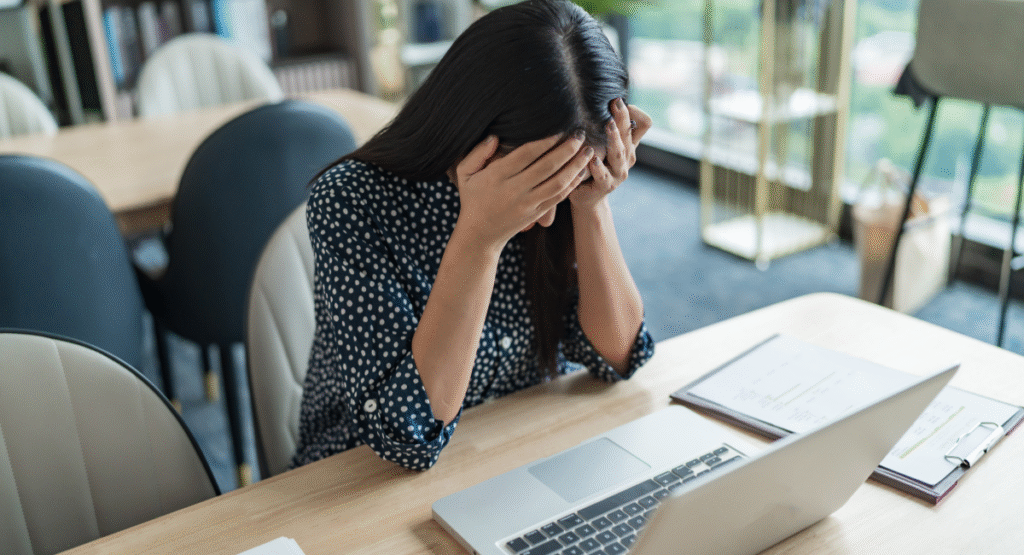
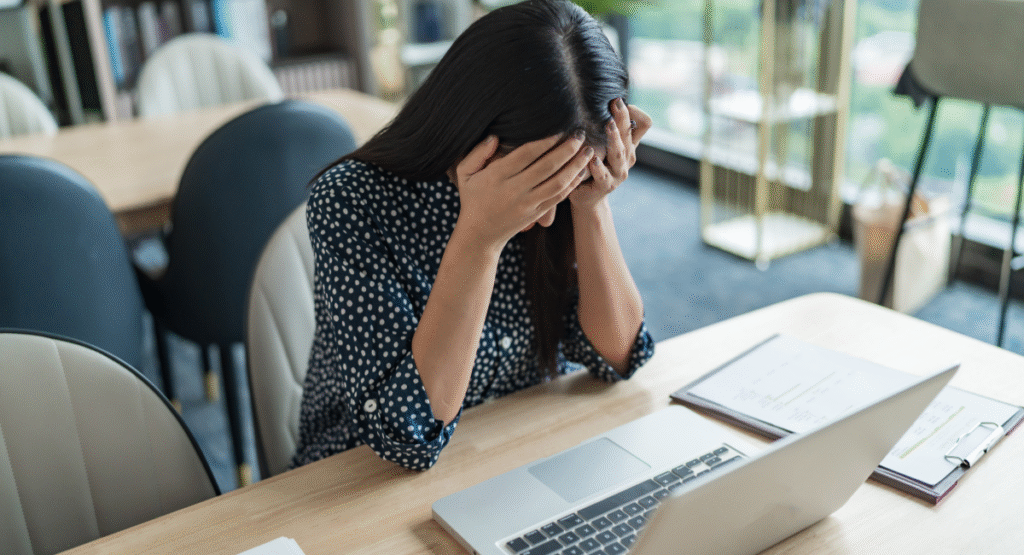
この章では、遺品整理で重要なものを誤って処分してしまった場合の対処法について紹介します。
重要なものを処分した際の対処には主に以下の内容があります。
- 法的書類を処分した場合の再発行や代替手段の検討
- 金融関係の書類を失った際の復旧手続きと損害回避策
- 身分証明書類の紛失時における各種手続きの進め方
- 親族関係の修復と今後のトラブル防止策
対処法(1)遺言書を捨てた場合



遺言書を誤って処分してしまった場合でも、まずは冷静に対応することが重要です。
自筆証書遺言を処分してしまった場合、原本の復元は不可能ですが、公正証書遺言であれば公証役場に正本や謄本が保管されているため再発行が可能です。
全国の公証役場で検索システムにより遺言書の有無を確認できますので、まず公証役場に問い合わせてください。
また、2020年7月から開始された法務局での自筆証書遺言保管制度を利用していた可能性もあるため、法務局にも問い合わせを行います。
故人が遺言書の写しを銀行の貸金庫や信頼できる第三者に預けていないかも確認が必要です。
見つからない場合は家庭裁判所に相談し、法定相続による遺産分割協議を進める準備をすることが重要です。
対処法(2)通帳・証券を処分した場合
通帳や証券類を処分してしまった場合でも、金融機関に連絡することで口座の存在確認と残高証明書の発行が可能です。
金融機関では顧客の口座情報を長期間保管しており、本人確認書類と相続関係を証明する戸籍謄本があれば、故人名義の口座の有無を調査できます。



全国銀行協会では「全国銀行個人信用情報センター」において、故人の取引があった可能性のある金融機関を調査するサービスを提供しています。
また、証券保管振替機構では上場株式等の保有状況を調査できる「開示請求」制度があります。
ゆうちょ銀行では「貯金等照会サービス」により全国の郵便局での取引状況を確認できるため、これらのサービスを活用して包括的に調査することをお勧めします。
対処法(3)身分証明書を紛失した場合
身分証明書を紛失した場合は、各発行機関に連絡して紛失届を提出し、必要に応じて再発行手続きを行います。
運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどの身分証明書には重要な個人情報が含まれており、不正利用を防ぐため速やかに紛失届を提出する必要があります。
運転免許証を紛失した場合は最寄りの警察署で遺失届を提出し、必要に応じて運転免許証明書を警察署で発行してもらいます。
マイナンバーカードの場合は市区町村役場でカード機能停止手続きを行い、パスポートの場合は外務省旅券事務所に紛失届を提出します。
健康保険証は14日以内に市区町村役場で資格喪失届を提出し、年金手帳は年金事務所で受給停止手続きを行う必要があります。
対処法(4)親族への謝罪と関係修復
重要な遺品を処分してしまった場合は、速やかに親族全員に報告し、誠実な謝罪と今後の対策を示すことで関係修復を図ります。
遺品整理での失敗は親族間の信頼関係に大きな影響を与える可能性があり、放置すると相続争いに発展する恐れがあります。
しかし、誠実な対応と具体的な解決策を示すことで関係修復は可能です。
処分してしまった品物の詳細、処分した経緯、現在の状況、今後の対応策を整理して親族会議を開催します。
重要書類を処分した場合は具体的な復旧方法と再発防止策を説明し、必要に応じて専門家を交えた話し合いの場を設けることも効果的です。
隠蔽や言い訳をせず、事実を正直に報告した上で、具体的な解決策と再発防止策を提示することが長期的な関係修復につながります。
\ 24時間365日受付中 /
判断に迷った時の対処法
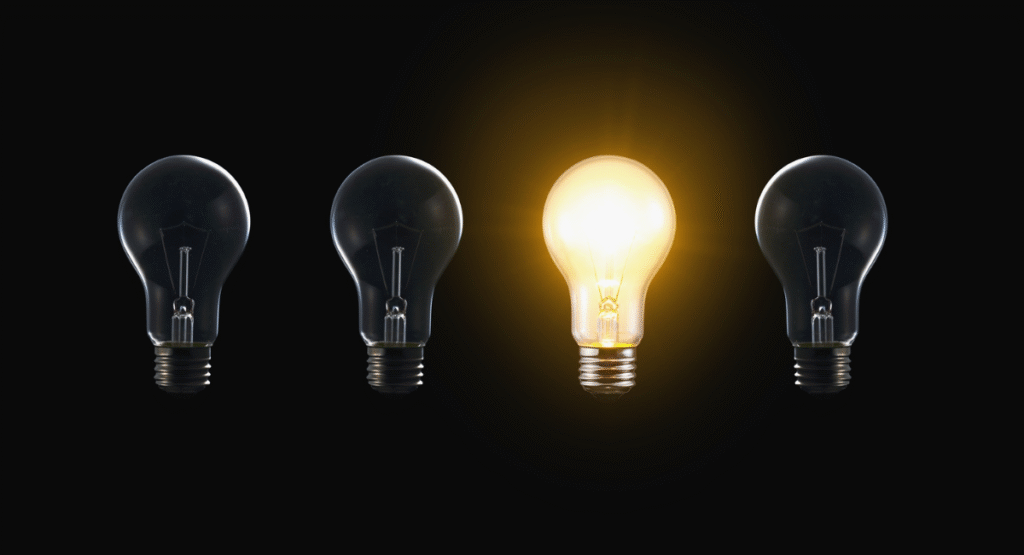
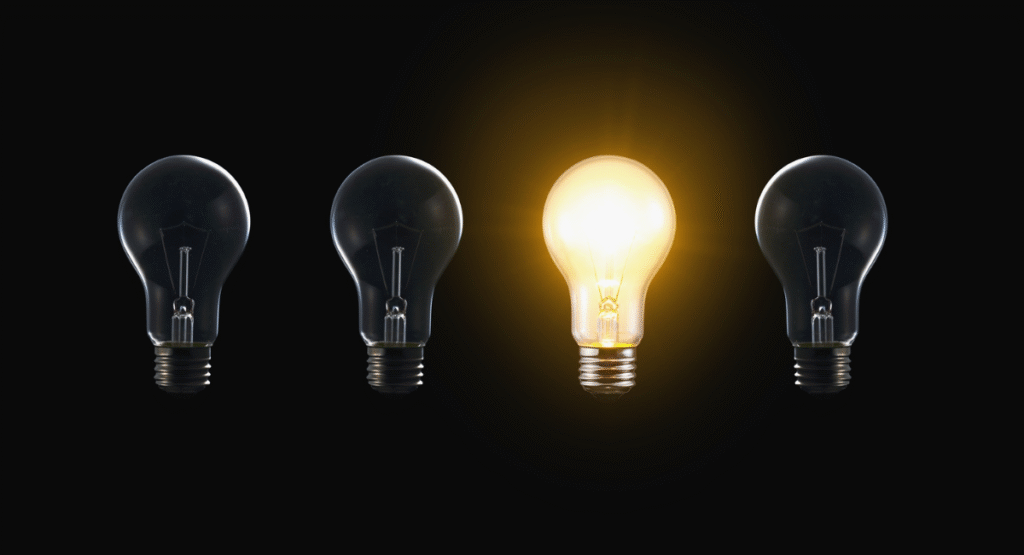
この章では、遺品整理で処分するかどうか判断に迷った時の対処法について紹介します。
判断に迷った際の対処法には主に以下の内容があります。
- 一時的に判断を保留する仕組みの構築と活用方法
- 親族間での円滑な話し合いと合意形成のプロセス
- 感情的価値と実用的価値を客観的に判断する基準
- 思い出の品を効率的に保存するデジタル化の手法
- 適切な一時保管場所の確保と保管期間の設定
方法(1)保留ボックスの活用
判断に迷う遺品は「保留ボックス」を用意して一時的に保管し、冷静になってから再度検討することが効果的です。
遺品整理を進める中で感情的になりやすく、その場での判断が適切でない場合があります。
保留ボックスを活用することで、急いで決断する必要がなくなり、後日冷静に判断できる時間を確保できます。
段ボール箱やプラスチックケースに「保留」のラベルを貼り、「価値不明の品物」「思い出の品」「親族要相談」などのカテゴリーに分けて管理します。
保留期間は1週間から1ヶ月程度とし、その間に専門家への相談や親族との話し合いを行います。
四十九日法要や親族が集まる機会を活用して、保留品について話し合うことも効果的です。



保留期間を明確に設定し、期限内に必ず再検討することが重要です。
方法(2)親族間での合意形成
重要な遺品の処分については、相続人全員の合意を得てから進めることで、後のトラブルを防ぐことができます。
遺品は法的には相続財産であり、価値のあるものを勝手に処分すると親族間の大きなトラブルになりかねません。
特に思い出の品や価値が不明な品物については、各人の思い入れが異なるため、事前の話し合いが不可欠です。
親族会議を開催し、遺品整理の方針や重要品の取り扱いについて話し合います。
連絡手段として、LINEグループやメールなどを活用して情報共有を図り、遠方に住む親族も参加できるよう配慮します。
判断に迷う品物については写真を撮影して共有し、各人の意見を聞いた上で多数決や話し合いで決定します。
形見分けについても、公平性を保つために順番を決めて選択する方法を採用することが重要です。
方法(3)感情的価値と実用性の見極め
遺品の感情的価値と実用的価値を客観的に評価し、保存の優先順位を決めることで効率的な遺品整理が可能になります。
遺品には経済的価値、実用的価値、感情的価値の3つの価値があり、これらを混同すると適切な判断ができません。
感情的になりがちな遺品整理において、客観的な評価基準を設けることで、後悔のない判断ができるようになります。
「高い経済的価値」「日常的な使用価値」「強い思い出価値」「家族への重要性」の4つの観点で各遺品を評価し、点数化して優先順位を決めます。
例えば、故人愛用の茶碗は経済的価値は低いが思い出価値が高く、高級腕時計は経済的価値が高いが思い出価値は普通といった具合に客観的に評価します。
限られた保管スペースの中で、本当に大切なものを残すための基準設定が必要です。
方法(4)写真・思い出の品のデジタル化
大量の写真や思い出の品は、デジタル化することで物理的な保管スペースを削減しながら思い出を永続的に保存できます。
近年のデジタル化技術の進歩により、高品質なデジタル保存が手軽に行えるようになりました。
デジタル化することで、劣化を防ぎ、複数の家族で共有することが可能になります。
写真のデジタル化には、スキャナーやスマートフォンアプリを活用します。
大量の写真がある場合は、専門のデジタル化サービスを利用することも効果的です。
思い出の品については、全方位から撮影し、説明文とともにデジタルアルバムとして保存します。
Google フォトやiCloudなどのクラウドサービスを活用して、家族間で共有できるようにします。
デジタル化は時間がかかる作業のため、家族で分担して進めることが重要です。
方法(5)一時保管の適切な場所と期間
判断に迷う遺品は、適切な環境で一定期間保管し、その間に専門家への相談や親族との話し合いを行うことが重要です。
急いで判断することで後悔する可能性を避けるため、一時保管の仕組みが必要です。
ただし、無期限の保管は新たな問題を生み出すため、明確な期限と保管条件を設定することが重要です。
トランクルームや貸倉庫を利用して、湿度や温度が管理された環境で保管します。
保管期間は通常3ヶ月から1年程度とし、四十九日法要、一周忌などの節目で再検討します。
保管品リストを作成し、写真付きで管理することで、後日確認しやすくします。



親族が住む地域にそれぞれ一時保管場所を設け、各自が検討できる環境を整えることも効果的です。
保管費用については事前に家族で話し合い、負担方法を決めておくことが大切です。
\ 24時間365日受付中 /
安全に遺品整理を進める方法


この章では、遺品整理を安全かつ効率的に進める方法について紹介します。
安全な遺品整理の進め方には主に以下の内容があります。
- 事前の綿密な計画立案と準備の重要性
- 信頼できる遺品整理業者の選定基準と注意点
- 専門家に相談すべき適切なタイミングと相談内容
- 効率的で安全な仕分け作業の進め方と管理方法
手順(1)作業前の計画立て
遺品整理を始める前に、相続手続きの期限、親族間の合意、作業スケジュールを含む包括的な計画を立てることが成功の鍵となります。
無計画に遺品整理を始めると、重要な書類を見落としたり、親族間でトラブルが発生したり、法的期限に間に合わない可能性があります。
特に相続放棄の期限である3ヶ月以内、相続税申告期限である10ヶ月以内、2024年度から義務化された相続登記の3年以内などの法的期限を考慮した計画が必要です。
まず相続人全員で話し合い、遺品整理の方針と役割分担を決定します。
賃貸住宅の場合は契約期限を確認し、逆算してスケジュールを組みます。
重要書類の確認、金融機関への連絡、デジタル遺品の調査など、優先順位を付けたチェックリストを作成し、保留ボックスの準備や一時保管場所の確保も事前に手配しておくことが重要です。
手順(2)遺品整理業者の選び方
信頼できる遺品整理業者を選ぶためには、必要な許可の確認、料金体系の透明性、実績と評判の調査が不可欠です。
近年、遺品整理業界への新規参入が増加している一方で、法的な知識が不足した業者や悪質な業者も存在します。
適切な許可を持たない業者に依頼すると、廃棄物処理法違反などの法的問題に巻き込まれる可能性があります。
一般廃棄物収集運搬業許可、古物商許可などの必要な許可を確認し、遺品整理士の資格を持つスタッフがいるかチェックします。
複数の業者から見積もりを取り、料金体系や作業内容を比較検討します。
過去の実績や口コミ、評判を調査し、実際に現地見積もりを依頼して担当者の対応を確認することが大切です。
作業中の損害保険の加入状況や、貴重品発見時の取り扱い方針についても事前に確認し、契約前には必ず書面で作業内容と料金を確認しましょう。
手順(3)専門家への相談タイミング
相続手続き、財産評価、法的問題については、遺品整理の初期段階から専門家への相談を行うことで、後のトラブルを防ぐことができます。
遺品整理は単なる片付け作業ではなく、相続、税務、法的手続きと密接に関連しています。
相続放棄や限定承認の判断、相続税の申告、不動産の相続登記など、専門的な知識が必要な手続きが多数あります。
- 故人に借金がある可能性がある場合
早期に弁護士に相談して相続放棄の検討を行います。 - 相続税申告が必要な場合
遺品整理開始から6ヶ月以内には税理士に相談し、財産評価の準備を始めます。 - 不動産がある場合
司法書士に相談して相続登記の準備を行い、デジタル遺品については専門業者への相談を検討します。 - 骨董品や美術品がある場合
専門の鑑定士に評価を依頼することも重要です。
手順(4)効率的な仕分け作業
体系的な仕分けシステムを構築し、重要度と緊急度に基づいた優先順位で作業を進めることで、安全で効率的な遺品整理が実現できます。
遺品整理では膨大な量の品物を限られた時間で仕分ける必要があり、効率的なシステムがないと重要な物を見落とすリスクが高くなります。
感情的になりやすい状況で客観的な判断を維持するためには、明確な基準と手順が必要です。
「重要書類」「金融関係」「デジタル機器」「思い出の品」「日用品」「処分品」「保留品」の7つのカテゴリーに分けて仕分けを行います。
各カテゴリーごとに専用のボックスを用意し、ラベルを貼って明確に管理します。
重要書類は最優先で確認し、発見次第、相続人全員に報告します。
デジタル機器は専門知識が必要なため、パスワード解除を含めて専門業者への依頼を検討し、思い出の品は写真撮影してリスト化することが効果的です。
\ 24時間365日受付中 /
まとめ


遺品整理で捨ててはいけないものは、遺言書や通帳などの法的書類、デジタル遺品、思い出の品など多岐にわたります。
最も重要なのは、遺言書やエンディングノートを絶対に処分しないことです。
判断に迷う場合は保留ボックスを活用し、親族間で十分に話し合ってから決断してください。
相続手続きの期限を意識した計画的な進行と、必要に応じた専門家への相談が、安全な遺品整理の鍵となります。



感情的になりがちな状況でも、明確な判断基準を持つことで、故人への想いを大切にしながら適切に作業を進めることができるでしょう。