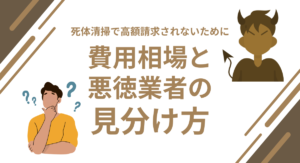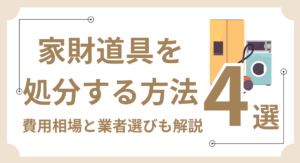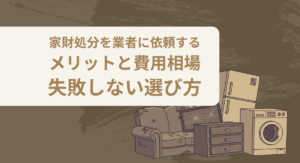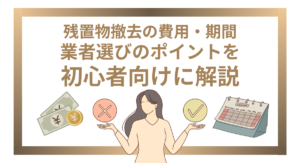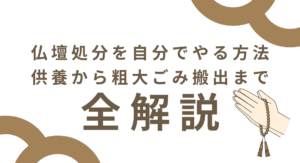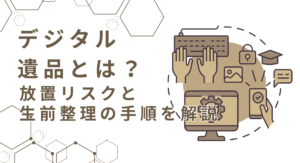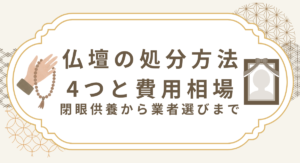「遺品整理がやばい状況になった」という声が急増している中、あなたは大切な家族の遺品を安心して任せられる業者を見つけられますか?
実は悪質業者による高額請求や不法投棄の被害は年々深刻化しており、何も知らずに依頼した遺族の約4割が「こんなはずじゃなかった」と後悔しています。



しかし正しい知識さえあれば、故人への想いを大切にしながら適正価格で丁寧な作業をしてくれる優良業者を必ず見つけることができます。
この記事では、悪質業者の巧妙な手口から身を守り、信頼できるパートナーを選ぶための具体的な判断基準をお伝えします。
遺品整理業界はなぜやばいのか


この章では、遺品整理業界の構造的な問題について紹介します。
遺品整理業界が「やばい」と言われる理由には主に以下の内容があります。
- 参入障壁が低く悪質業者が急増している現状
- 法規制が不十分で監督体制が甘い業界構造
- 消費者の知識不足を狙った詐欺的手法の蔓延
理由(1)参入障壁が低く悪質業者が急増
遺品整理業界は参入障壁が極めて低く、急速な市場拡大とともに悪質業者が急増しています。
高齢化社会の進展により、2023年の65歳以上の高齢者人口は約3,600万人に達し、総人口の約28.4%を占めるまでになりました。
2025年には後期高齢者の人口が約2,180万人に達すると見込まれており、遺品整理の需要は今後さらに拡大していく状況です。
この需要拡大に対応するため、2021年時点で遺品整理業者は約12,500社を超え、新規参入が相次いでいます。
しかし、遺品整理業は無資格・無免許でも開業でき、明確なサービス内容の基準も存在しないため、経験や知識が不十分な業者も多数混在しており、深刻なトラブルが発生する原因となっています。
理由(2)法規制が不十分で監督体制が甘い
遺品整理業界には専門的な業法が存在せず、法規制が不十分なため監督体制が甘く、悪質業者が参入しやすい環境が形成されています。
遺品整理業を適正に営むためには、一般廃棄物収集運搬業許可や古物商許可など複数の許可が必要ですが、これらの許可取得要件は複雑で、特に一般廃棄物収集運搬業許可は市町村の裁量が大きく、新規許可が出にくい状況があります。
総務省の調査によると、調査対象の69事業者のうち、遺品の搬出まで行っている45事業者の中でも、必要な許可を取得していない事業者が存在することが明らかになっています。
法律による明確な基準や規制がないため、どの業者でも自由に「遺品整理業」を名乗ることができ、この状況が悪質業者の参入を容易にしているのが現状です。
理由(3)消費者の知識不足を狙った詐欺
遺品整理業界では、消費者の知識不足や心理的な弱さにつけ込んだ詐欺的な手法が横行しており、トラブル経験者は約4割に上っています。
遺品整理は故人が亡くなった直後の気持ちが落ち込んでいる時期に行うため、遺族の精神状態によっては正常な判断ができず、悪質業者の被害に遭いやすい状況があります。



特に葬儀や各種手続きの合間に急いで整理を進めなければならない場合、業者に「全部お任せしたい」と依存してしまいがちです。
「みんなの遺品整理」の調査結果では、約半数の依頼者が追加請求を経験しており、5万円前後の追加請求が最も多く、中には20万円以上の高額請求をされたケースも報告されています。
多くの人は遺品整理の基礎知識や料金相場を知らないため、悪徳業者の不正請求に対しても「これが妥当なのかな」と思いがちで、この知識格差が悪質業者に利用されているのです。
\ 24時間365日受付中 /
やばい業者によるトラブル事例


この章では、実際に発生している悪質な遺品整理業者によるトラブル事例について紹介します。
やばい業者によるトラブル事例には主に以下の内容があります。
- 作業後の理不尽な高額追加請求
- 遺品の盗難・紛失・無断破棄による損害
- 不法投棄による環境汚染と法的責任
- 不当に安い価格での強制買取
- 契約内容と異なる粗雑な作業
事例(1)作業後の高額追加請求
見積もり金額から大幅に膨らんだ追加請求は、悪質業者による最も多いトラブル事例です。
「みんなの遺品整理」の調査によると、依頼者の約半数が追加請求を経験しており、5万円前後の追加費用を請求されるケースが最も多く、中には20万円以上の高額請求を受けた事例も報告されています。
悪質業者は最初に極端に安い見積もりを提示して契約を取り付け、作業開始後に「想定以上に物が多い」「特殊な作業が発生した」などの理由をつけて高額な追加料金を請求する手口を使用します。
消費者庁には100万円以上の追加請求となった事例も寄せられており、見積もりの2〜3倍の費用を請求される深刻なトラブルが発生しています。
このような被害を防ぐためには、事前に詳細な見積書を取得し、追加料金が発生する条件を明確にしてもらうことが重要です。
事例(2)遺品の盗難・紛失・無断破棄
故人の貴重品や思い出の品が盗難されたり、重要な書類が無断で破棄されるトラブルが多発しており、遺族に深刻な精神的ダメージを与えています。
遺品整理の現場では、故人にとって大切な思い出の品や高価な貴金属、重要な書類などの紛失が頻繁に発生し、悪質業者による貴重品の持ち去りや故人のアルバムや思い出の品の乱雑な扱いが報告されています。
また、遺品を乱雑に扱われて品物や室内に傷がついたり、壊されたりするケースや、遺族に無断で価値のある遺品を処分してしまう事例も発生しています。
悪質業者は作業員の教育が不十分で、遺品の価値を理解せずに扱うことが多いため、このようなトラブルを避けるためには、貴重品は事前に自分で取り出しておき、残すべき遺品と処分対象を明確に分別することが必要です。
事例(3)不法投棄による環境汚染
適切な処分費用を削減するために、悪質業者が山林や空き地に遺品を不法投棄するケースが発生しており、最終的に依頼者が法的責任を問われる可能性があります。
一般廃棄物収集運搬業許可を持たない業者は、引き取った遺品を適切な処理施設に運び込むことができないため、処理コストを削減する目的で不法投棄を行うことがあります。
悪徳遺品整理業者が片付けた不用品を適切に処分せず山林や空き地に放置する事例が実際に報告されており、このような不法投棄が発見された場合には、環境問題だけでなく法的な問題にも発展し、依頼者がその責任を問われることになってしまいます。
故人の供養のためにも、遺品整理は正式な許可を持った業者に依頼し、処分方法や処分先について明確な説明を求め、処分証明書の発行を依頼することが重要な対策となります。
事例(4)不当に安い価格での強制買取
遺品の価値を適正に評価せず、相場よりもはるかに安い価格で強制的に買取を行う悪質な手法が横行しています。



遺品整理の一環として故人が残した物品を買取する際、遺族が期待していた価格と実際の買取価格に大きな差がある場合にトラブルが発生します。
悪質業者は遺族の知識不足を利用して、価値のある骨董品やブランド品を不当に安い価格で買い取ろうとし、「一括買取」として値がつかない物と価値のある物をまとめて買い取り、差額を費用として請求する手法も使われています。
実際には価値のある品物を二束三文で買い取り、高値で転売する事例が報告されており、このような被害を防ぐためには、遺品の買取を行う際に事前に現在の市場相場や商品の状態について詳しい説明を求め、複数の買取業者から査定を取ることが重要です。
古物商許可を持つ業者であることを確認し、買取価格に納得がいかない場合は売却を断る判断も必要です。
事例(5)契約内容と異なる粗雑な作業
契約時に約束したサービス内容と大きく異なる粗雑な作業により、遺品が適切に扱われず、遺族の感情を傷つけるトラブルが発生しています。
請求金額に見合わない低いクオリティのサービスを提供する業者が存在し、作業効率が著しく悪い、物品の取り扱いが雑、スタッフの教育が行き届いておらず言葉遣いが乱暴で態度が悪いといった問題が発生しています。
具体的には、故人のアルバムや思い出の品を乱雑に扱ったり、物が散らかったまま放置されている箇所があったり、遺品整理時に物を破損させる事例が報告されています。
また、遺族とのコミュニケーション不足により要望に沿わないサービスが提供されるケースも多く、遺族の心情に配慮しない対応により精神的な被害を受ける事例もあります。
このようなトラブルを避けるためには、契約時に作業内容を詳細に確認し、遺品整理士の資格を持つスタッフが在籍している業者を選ぶことが重要です。
\ 24時間365日受付中 /
悪質業者を見分ける方法


この章では、悪質な遺品整理業者を見分けるための具体的な方法について紹介します。
悪質業者を見分ける方法には主に以下の内容があります。
- 必要な許可証や資格の確認による信頼性の判断
- 極端に安い見積もりに対する適切な警戒
- 書面契約を避ける業者の危険な特徴
- ホームページの情報不足による業者の実態把握
- 強引な営業手法への適切な対処方法
方法(1)必要な許可証や資格の確認
遺品整理業を適正に営むために必要な許可証や資格の有無を確認することで、悪質業者を効果的に見分けることができます。
遺品整理業は無資格でも開業できますが、実際の作業には複数の許可が必要です。
確認すべき許可証
- 一般廃棄物収集運搬業許可で、これは不用品の回収・運搬に必須の許可です。
- 古物商許可は遺品の買取を行う際に必要となります。
- 遺品整理士認定協会の認定資格を持つスタッフが在籍しているかも重要なポイントです。
2024年6月時点で遺品整理士は60,000名を突破していますが、産業廃棄物収集運搬許可と混同しやすいため注意が必要です。産業廃棄物の許可だけでは一般家庭からの遺品回収はできません。



業者選びの際は、公式サイトの会社概要で許可証情報を確認し、行政指導歴がないかもチェックしましょう。
方法(2)極端に安い見積もりへの警戒
相場から大きく外れた極端に安い見積もりは、後から高額な追加請求を行う悪質業者の典型的な手口です。
「格安で遺品整理します」という謳い文句や相場の半額以下という破格の見積りには十分な警戒が必要です。
遺品整理の間取り別適正価格相場
- 1R・1Kで30,000~80,000円
- 1DK・1LDKで50,000~120,000円
- 2DK・2LDKで90,000~250,000円
- 3DK・3LDKで150,000~400,000円
- 4LDK以上で220,000~600,000円
悪質業者は極端に安い見積もりで契約を取り付けた後、作業開始時に「想定以上に物が多い」などの理由をつけて追加料金を請求します。
相場から大きく外れた金額には必ず理由があるため、複数業者からの相見積もりを取得して適正価格を把握することが重要です。
方法(3)書面契約を避ける業者の特徴
契約書の交付を避け、口約束で済ませようとする業者は、トラブル発生時の責任逃れを図る悪質業者の典型的な特徴です。
やばい遺品整理業者は作業内容や料金に関する責任をうやむやにするため、契約書を交付せずに進めようとします。
信頼できる業者であれば見積書や領収書などを積極的に発行してくれますが、悪徳業者の中には見積書すら出さない場合があります。
見積書がない場合は業者の言い値になってしまい、最終的な費用が作業終了まで分からない状況となります。
発行を依頼しても拒否される場合は悪徳業者の可能性が高いため、即座にキャンセルすることが推奨されます。
見積書、契約書、領収書の発行を必ず求め、これらの書面交付を拒む業者とは契約しないことが重要です。
契約内容に不明な点がある場合は書面での説明を求め、口約束での合意は避けましょう。
方法(4)ホームページの情報不足を確認
ホームページに基本的な会社情報が不足している業者は、トラブル発生時に逃亡を図ることを想定した悪質業者である可能性が高いです。
住所や連絡先が記載されていない業者は、トラブルが起きた際に証拠隠滅を図る可能性があります。
形だけのサイトは短時間で作成でき、問題が発生すればすぐに消去して足跡を消すことができるため、十分な情報開示を行わない傾向があります。
公式サイトで料金が曖昧または記載されていない、固定電話ではなく携帯電話のみの連絡先、処分に必要な資格や許可証の情報が掲載されていないなどの場合は要注意です。
信頼できる業者を選ぶ際は、ホームページの内容が充実していることを確認し、会社の所在地、代表者名、連絡先、事業内容、許可証情報、実績などが明確に記載されているかをチェックすることが重要です。



情報が不足している業者は候補から除外しましょう。
方法(5)強引な営業への対処
契約を急かす強引な営業手法は悪質業者の典型的な特徴であり、冷静な判断を妨げる手口として警戒すべきです。
悪徳遺品整理業者は執拗な電話連絡や何度もインターホンを鳴らすなど、強引な営業を行うことがあります。「今日中の契約で割引」「今契約したら安くなる」などの文言で迫り、焦らせて十分な検討時間を与えないのは典型的な手口です。
中には消費者を脅したり不安を煽ったりする手法で契約を急かす業者もおり、故人が亡くなった情報を入手して自宅を訪問し、半ば強制的に契約を進めようとするケースも報告されています。
このようなトークは「今契約しないと損をする」と思わせ、冷静な判断を妨げる手口です。
強引な営業を受けた場合は、その場で契約せずに一度断って時間をおき、複数業者からの見積もりを取得して比較検討することが重要です。
訪問販売の場合はクーリングオフの対象となる可能性もあります。
\ 24時間365日受付中 /
遺品整理の料金相場


この章では、遺品整理の料金相場について紹介します。
遺品整理の料金相場には主に以下の内容があります。
- 間取り別の基本料金と計算方法の詳細
- 見積書に記載される項目別の内訳と内容
- 追加料金が発生する条件と適正性の判断基準
相場(1)間取り別の料金と計算方法
遺品整理の料金は主に間取り・物量・作業人員数によって決まり、適正な相場を知ることで悪質業者の不当な請求を見分けることができます。
間取り別費用相場
- 1R・1Kで30,000~80,000円
- 1DK・1LDKで50,000~120,000円
- 2DK・2LDKで90,000~250,000円
- 3DK・3LDKで150,000~400,000円
- 4LDK以上で220,000~600,000円
ただし、同じ間取りでも遺品の量によって大きく変動するため注意が必要です。料金計算のベースとなるのは作業員の人件費で、「何人の作業員が必要で、どのくらい時間がかかるか」が見積もりの重要なポイントとなります。
重要な基準は部屋の間取り、遺品の量、特殊清掃の有無の3点です。
複数業者から相見積もりを取って相場感を把握し、極端に安い見積もりや高額な見積もりには十分注意することが重要です。
相場(2)見積書の項目別内訳
透明性の高い見積書には基本料金・人件費・車両費・処分費・オプション費用が明確に分かれて記載されており、項目別の内訳を理解することで適正な業者を見分けることができます。
一般的な見積書の項目
- 基本作業費
人件費・時間 - 車両費
トラックの大きさ・台数 - 処分費
廃棄物の種類・量 - 買取費用
価値のある遺品の査定額 - 特殊作業費
エアコン取り外し、清掃など - 立地条件による追加費用
階段作業、駐車場からの距離など
オプション費用
- エアコンの取り外し
- ハウスクリーニング
- 現場供養などが



優良な業者は事前の見積もり段階で請求内容や作業範囲を明確にし、後から追加の請求を行うことはありません。
見積書の内訳が不明瞭な業者や項目が曖昧な業者は避け、各項目の単価や計算根拠について明確な回答が得られない業者との契約は控えることが重要です。
相場(3)追加料金発生の条件
適正な追加料金は事前説明なく発生した想定外の作業に限定されるべきですが、悪質業者は契約後に理不尽な追加請求を行うため、追加料金の条件を事前に明確化することが重要です。
調査によると、依頼者の約半数が追加請求を経験しており、5万円前後の追加請求が最も多く、中には20万円以上を請求されたケースもあります。
適正な追加料金の例として、見積もり時に確認できなかった隠れた場所からの大量の遺品発見、事前に伝えられていなかった特殊清掃の必要性、想定外の解体作業の発生などがあります。
一方で、悪質業者は「予期せぬ作業が発生した」との理由で高額な請求を行ったり、当初から予想できた作業に対する後付けの請求を行います。



トラブル回避のためには、どこまで業者に依頼するかを明確にし、作業範囲やゴールをあらかじめ定めることが重要です。
契約前に追加料金が発生する具体的な条件と単価を書面で確認しましょう。
\ 24時間365日受付中 /
信頼できる業者の選び方


この章では、信頼できる遺品整理業者を選ぶための具体的な方法について紹介します。
信頼できる業者の選び方には主に以下の内容があります。
- 複数業者からの相見積もりによる比較検討
- 遺品整理士資格と業界団体への加盟状況の確認
- 口コミ評判の適切な調査方法と見極めポイント
- 契約前に必ず確認すべき重要事項
選び方(1)複数業者からの相見積もり



複数業者から相見積もりを取ることで、適正価格の把握と悪質業者の排除が可能になり、最適な業者選択ができます。
遺品整理業者を選ぶ際は、必ず3~5社から見積もりを取り、費用の相場を把握することが重要です。
複数の見積もりを比較することで、極端に高い業者だけでなく、安すぎる業者にも注意を向けることができます。
見積もり確認のポイントとして、責任者の印が押されているか、有効期限内であるか、依頼したサービスやオプションサービス、キャンセル料の記載があるかをチェックしましょう。
トラブルを未然に防ぎ、優良業者を選ぶためには相見積もりの実施、遺品整理士の在籍有無、業者の対応を確認することが大切です。
相見積もりの際は、同じ条件で各業者に依頼し、価格だけでなく作業内容、スタッフの対応、会社の信頼性を総合的に判断することが重要です。
選び方(2)遺品整理士資格と業界団体
遺品整理士の資格を持つスタッフが在籍し、信頼できる業界団体に加盟している業者は、専門知識と法令遵守の意識が高く、安心して依頼できます。



遺品整理士は一般財団法人遺品整理士認定協会の認定資格で、法令に沿った廃棄物処理方法や遺品の取り扱いに関する法律について講義を受け、合格した人だけが取得できる資格です。
2024年6月時点で遺品整理士は60,000名を突破しており、遺品整理業者にとって必須ではありませんが、持っていると信頼性が大幅にアップします。
遺品整理士認定協会は遺品整理業界の健全化を目的として設立された団体で、法令順守をしている30,000名を超える会員、1,000社を超える法人会員が加盟しています。
遺品整理士がいれば、相続人の気持ちが落ち込んでいる場合でも寄り添った対応を行ってもらえるため、業者のホームページやパンフレットで在籍状況を確認しましょう。
選び方(3)口コミ評判の調査方法
口コミ評判の調査は重要ですが、自作自演の評価やステマが横行しているため、複数の情報源から客観的に判断し、信頼性の高い口コミを見分ける必要があります。
遺品整理業者選びで口コミ情報だけを鵜呑みにするのは危険で、近年は架空のお客様の声を掲載するステマが増えているため、慎重な情報収集が必要です。
やばい遺品整理業者には悪い口コミが多い傾向があり、実際に利用した方の意見は非常に参考になります。
契約前には口コミサイト、SNS、Googleマップなどで業者の評判をチェックしましょう。
信頼性の高い口コミの特徴
- 具体的な作業内容や料金への言及
- 写真付きのレビュー
- 長期間にわたる複数の評価
逆に注意すべき口コミ
- 短期間に集中した高評価
- 具体性に欠ける抽象的な内容
- 極端に感情的な表現
複数の情報源を活用し、全体的な傾向を把握することが重要です。
選び方(4)契約前の確認事項
契約前の確認事項を徹底することで、トラブルを未然に防ぎ、安心して遺品整理を依頼できる信頼関係を構築できます。
遺族が質問や要望を気軽に相談できる専用窓口があるかを確認し、コミュニケーションがスムーズに行える体制があるかをチェックしましょう。
遺品整理のゴールを明確に定めることも重要で、部屋の整理だけなのか、不用品の廃棄も含むのか、完全な原状回復まで必要なのかを事前に決めておくことで、予期しない追加料金を避けることができます。
契約前の必須確認事項
- 作業内容の詳細説明
- 料金体系の透明性
- 追加料金発生条件
- 作業日程とキャンセル規定
- 損害保険の加入状況
- 契約書の詳細
- 作業員の身元確認
- 作業後の清掃範囲
- 遺品の処分方法と証明書
- アフターフォロー
作業範囲の事前確認
- 処分する遺品
- 残す遺品
契約前には必ず書面での契約書を交わし、不明な点は質問して明確な回答を得ましょう。
\ 24時間365日受付中 /
トラブル発生時の対処法


この章では、遺品整理業者とのトラブル発生時の具体的な対処法について紹介します。
トラブル発生時の対処法には主に以下の内容があります。
- 国民生活センターへの相談手順と活用方法
- 警察への被害届提出と証拠保全の重要性
- クーリングオフ制度の適用条件と手続き方法
- 弁護士相談が必要となるケースと選び方
対処法(1)国民生活センターへの相談
国民生活センターは消費者トラブルの第一相談窓口として、遺品整理業者とのトラブルに対して無料で相談対応を行い、解決に向けた適切なアドバイスを提供しています。
年間100件を超える遺品整理関連の相談が寄せられており、2021年度には全国の消費生活センター等に不用品回収サービスに関する相談が2,231件も報告されています。
相談可能な内容
- 高額な追加請求
- 契約内容と異なる作業
- 遺品の盗難や紛失
- 不法投棄
- 強引な営業による契約
全国共通の消費者ホットライン「188」に電話することで、最寄りの消費生活センターにつながり、専門の相談員からアドバイスを受けることができます。
相談時には契約書、見積書、領収書、業者とのやり取りの記録、写真などの証拠資料を準備しておくことが重要です。
相談は無料で匿名でも可能なため、躊躇せずに早期に相談することで被害の拡大を防げます。
対処法(2)警察への被害届と証拠保全
遺品の盗難や詐欺など犯罪性が疑われる場合は警察への被害届提出が必要であり、事前の証拠保全が被害立証の鍵となります。
貴重品を勝手に持ち去ったり、故人の重要書類を無断廃棄する行為は窃盗罪や器物損壊罪に該当する可能性があります。
警察への被害届が必要なケース
- 貴重品や現金の盗難
- 重要書類の無断廃棄
- 契約書と大幅に異なる高額請求
- 脅迫的な取り立て
- 不法投棄
証拠保全の方法として、以下のような準備が重要です。
- 作業前後の写真撮影
- 契約書や見積書の保管
- 業者とのやり取りの録音や記録
- 被害状況の詳細な記録
- 第三者の証言
被害届提出時にはこれらの証拠資料を整理して持参する必要があります。
明らかに犯罪性がある場合は躊躇せずに警察に相談すべきですが、民事的な契約トラブルと刑事事件の境界は複雑なため、まず消費生活センターや弁護士に相談して適切な対応方針を決めることが重要です。
対処法(3)クーリングオフの適用
訪問販売による遺品整理契約はクーリングオフの対象となり、契約から8日以内であれば無条件で契約解除が可能です。
遺品整理は事業所ではなく消費者の自宅で契約を交わすケースが多いため、訪問販売に該当する場合があり、特定商取引法によって厳しく規制されています。
契約から8日以内であればクーリングオフ制度が適用され、キャンセル料も違約金も支払う必要がありません。
クーリングオフが適用される条件
- 自宅や職場など事業者の営業所以外で契約した場合
- 電話勧誘により契約した場合
- 契約金額が3,000円以上
クーリングオフは契約を交わした日から8日以内(契約当日を1日目と数える)に事業者に通知することで成立し、証拠を残すため電話や口頭ではなく書面で通知し、内容証明郵便で送付する必要があります。
契約後にトラブルが発生した場合は、まずクーリングオフの適用可能性を確認し、期限内であれば速やかに手続きを行うことが重要です。
対処法(4)弁護士相談が必要なケース
高額な損害が発生した場合や業者が交渉に応じない場合、複雑な法的問題が絡む場合は弁護士への相談が必要となり、専門的な法的対応が求められます。
消費者庁には100万円以上の追加請求となった事例も寄せられており、このような高額な被害については個人での対応が困難です。
また、不法投棄された場合には依頼者が法的責任を問われることもあるため、専門的な判断が必要となります。
弁護士相談が必要なケースとして、以下のような事例があります。
- 被害額が50万円以上の高額な場合
- 業者が連絡不通や交渉拒否の場合
- 不法投棄による法的責任が問われる場合
- 複数の法的問題が重複している場合
- 時効の問題がある場合
弁護士選びのポイント
- 消費者問題に詳しい弁護士
- 遺品整理トラブルの経験がある弁護士
- 初回相談料が無料または安価な弁護士
まずは弁護士会の法律相談や法テラスなどの無料・低額相談を活用し、事案の見通しと費用対効果を検討してから正式な依頼を判断することが賢明です。
\ 24時間365日受付中 /
まとめ


遺品整理業界が「やばい」と言われる背景には、参入障壁の低さや法規制の不備、消費者の知識不足を狙った悪質業者の存在があります。
実際に約4割の利用者がトラブルを経験し、高額請求や遺品の盗難などの被害が報告されています。しかし、必要な許可証の確認、極端に安い見積もりへの警戒、書面契約の徹底など、悪質業者を見分けるポイントを押さえれば被害を防げます。
複数業者からの相見積もりや遺品整理士資格の確認により信頼できる業者を選び、万が一のトラブル時は国民生活センターやクーリングオフ制度を活用しましょう。
正しい知識を身につけることで、故人の遺品を大切に扱ってくれる優良業者と安心して契約することができます。